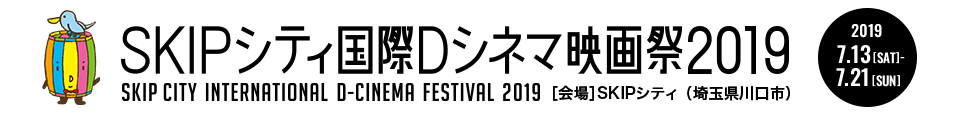ニュース
【インタビュー】国内コンペティション長編部門『ミは未来のミ』磯部鉄平監督

『ミは未来のミ』
磯部鉄平 監督インタビュー
——磯部監督は昨年の本映画祭の国内コンペティション短編部門で『予定は未定』が優秀作品賞を受賞しました。そこから今回の『ミは未来のミ』に至る経緯を少しお話しいただければと。
2016年から短編を撮り始めたんですけど、計6本ぐらい撮ったんですよ。ですから、そろそろ次の段階にいかないといけないんだろうなと思っていて。その中でやっぱり長編を撮っていないのはひっかかっていたんです。周りの先輩とかからも「長編撮って一人前だ」とか、「お前はいつになったら長編を撮るんだ」と言われたりしてたので、そろそろチャレンジせなあかんのかなと。
そんなときに、『予定は未定』がSKIPシティで優秀作品賞を獲ったのでひとつ区切りがついたというか。腹を決めて長編に挑戦してみようと思いましたね。
——それで長編の制作に動きだした?
実際は『予定は未定』の受賞前なんですけど、八王子Short Film映画祭が企画公募をしていることを知人から聞いて。企画が通ったら作品の助成があると。あと、僕は大阪が拠点なんですけど、少し前に東京で撮影したことがあって。これがすばらしくて、東京の俳優さんを使って東京で撮影するのもいいなぁと思ってたんです。それで企画が通ったら、短編といいつつ、長編を撮ってやろうと思ったんです(苦笑)。まあ、その時点ではまだ企画が通るかわからないので、あくまで目論見だったんですけど。それで、確か企画提出締め切りの当日だったんですけど、一気にプロットを書き上げて応募したところ、通りまして。その時点から確信犯的に短編を撮るふりをして、長編に挑んでいました。
最終的に八王子Short Film映画祭の方に伝えたら、「ハハハ」と笑って許してくれて。快く作品を送り出してくれたので、八王子Short Film映画祭にもものすごく感謝しています。
——実際に長編に挑まれてみてどうでしたか?
やっぱりしんどかったですね。現場の苦労は変わらないと思うんですけど、撮影期間が長くなりますから、短編のように数日で一気にという勢いだけでいけない。
監督の僕自身は気持ちが常に盛り上がっているから大丈夫なんですけど、スタッフや俳優さんのモチベーションをキープさせるのが大変。そのためには撮休とかもほんまに必要なんやと実感しました。みんなのことをちゃんとみて、気を配って、考えてやらないとダメだなと思いました。
——その磯部さんが1日で書き上げた企画ですが、シナリオにはどうやって仕上げていったのでしょう?脚本は『予定は未定』の永井和男さんになります。
実は、初めての長編でやりたいと思っていたアイデアなんですよ。どこかの映画祭から大阪への帰路で、車で5~6時間ぐらいかな、永井君とずっと話していて、この話をしたらめちゃくちゃ面白がってくれた。だから締め切り当日に企画を一気に書けたんですけどね。
そもそもは、僕が高校3年生のときの話なんです。まあ、悪友で集まって他愛のない話しをしていたら、なんかの拍子に「今死んだら」みたいな話題になって。「エロ本、親に見つかるのはやだな」と(笑)。「じゃあまじで死んだら、それぞれが責任をもって処分しよう」とかなって、隠し場所をそれぞれに伝えあった。そうしたら、ほんまにひとりの友人が亡くなって、お葬式のときに、家に潜り込んで処分したんですよ。
なんかこの体験はいつか映画にしたいなと思っていて。実は、近いことを過去の短編でやっているんですね。ただ、今回はフィクションではあるんですけど、もっとノンフィクションといいますか。自分のほんまの体験をまんま描きたいなと。
——ひとりの映画作家として実体験を描くことへの興味もあった?
いまプロで活躍されている先輩から、「商業に行く前、自主でやりたいことをやり切った」とか、「自主ではほんとうに自分の描きたいこと、伝えたいメッセージを込めた」とかよくきいて。総じて、みなさん、恥ずかしがらずに自身のパーソナルなものを1度全部吐き出している。自分はそれまだできていない。覚悟が足りないなという思いもあって、今やらないでどうするというところはありましたね。
——では、ほぼ実体験に基づいていると。
そうですね。高校3年の拓也を主人公において、ひとつの友の弔いを描いてますけど、中心には実体験があって。そこにスタッフの高校時代のしょーもない体験とか「あのころ、君は若かった」的なエピソードも加えて、永井さんがうまくまとめてくれた感じです。
——全体は高校生のどうしようもないモラトリアム的な時間がユーモアをもって描かれている。ただ、話が進むにつれて、その笑いのすぐそばに実は哀しみがあることに気づかされます。この二つが合わさったとき、何気ないと思ってけど、実はいとおしい、かけがえのない瞬間が浮かびあがります。
僕としては、これまでの人生で観てきたことを素直に描こうと思ったんです。ドラマや映画では、愛する人が亡くなると大声で叫んだり、大泣きしたりするのが定番ですけど、今回、この作品を作るにあたって振り返ったとき、僕にはそんな場面に遭遇したことが1度もないんですよ。実際は、声も出なかったというか。悲しいことは悲しかったんですけど、すぐには友人が死んだことが現実とは思えなかった。
子どものときに祖母が亡くなったときのお葬式でも、神妙な場面にも関わらず、しょうもないことで喧嘩が起こったり、親戚で笑っていたと思ったら、次の瞬間に泣いてたり、よくわからない(笑)。
例えば、友人の葬儀の帰り道、何もしゃべらなかった。あのときの空気や匂いは今も忘れていない。そういう瞬間を映画に封じ込むことはできないかなと。それは、見てくれるみなさんの中にある、なにか大切な記憶にもつながってくれるような気がしました。

『ミは未来のミ』場面写真 ©八王子日本閣
——主人公の拓也を演じているのは櫻井保幸さん。実は同じく国内長編コンペに選出された『サクリファイス』にも出演しています。
そうみたいで、『サクリファイス』、めっちゃ見たいです(笑)。実は、『ミは未来のミ』よりも先に撮り終えていて、まだ完成していない作品があるんですけど、それに手島実優さんに出演していただいて。その撮影時、手島さんに「櫻井さんはすばらしい俳優だ」とお聞きしていたんです。それもあって、手島さんと櫻井さんが共演している『赤色彗星倶楽部』を観て、なるほどいい役者さんだなと思っていたんです。
それで、去年のSKIPシティの映画祭の上映の際、舞台挨拶かなんかで、僕が「いま映画を作ろうとしていて主人公を探しています。興味ある人は声掛けください」みたいなこといったんですよ。そうしたら、櫻井さんの知り合いの方が見に来てくれてて、「櫻井どうですか?」と。ああ、これは縁だなと思って「紹介してください」となったんです。
——実際お会いしてみてはいかがでしたか?
オーディションを受けてもらったんですけど、本人は否定するかもしれないんですけど、いい意味で肩の力は入ってないんですけど、「お前に呼ばれたからきた。こっちに選ぶ権利はあるからな」という雰囲気を感じて(笑)。それが高校生のちょっといきがったところと、グダグダなところにもつながって拓也役にぴったりじゃないかと思いました。
——ある意味、監督の分身ともいえる役ですが。
あとで言ったんですけど。撮影のときは言いませんでしたね。
——では、役についてはどんな説明を?
オーディションでぴったりだったので、そのまんまでいてくれればいいなと思ったんですよ。オーディションでいくつかシーンを演じてもらったんですけど、対応力もあることが確信できて、これそのままいけるんちゃうかと。だから自分としてはそこでいけると思っているから、あまり構うことなく放置していたんですよ。たぶん櫻井さんは大丈夫だから、ほかの気になるところに注意を向けようと。
ただ、櫻井さんとしてはいろいろと話したいことがあったみたいで。クランクイン前日に電話かかってきて、丁寧な言葉の中に少々、怒りを感じたりとか。クランクアップの打ち上げのときは「なんで僕だけ役についての話し合いを簡単な説明くらいで済ますんですか?」とお叱りを受けました(笑)。なので、ちょっと放置しすぎたなと、反省してます。
——初長編を撮り終えたわけですが、そもそも映画監督を目指したきっかけは?
映画は子どものころから好きだったんですよ。長男なんですけど、おかんが映画が大好き。対して、おとんと弟たちはまったく興味がなくて。だから、僕だけ母に連れられて梅田の映画館によくいっていたんです。
それでレンタルビデオがはやりだしたころ、お小遣いはまったくくれない家庭だったんですけど(笑)。ビデオをレンタルする料金だけは出してくれる。それで毎日1本レンタルしてみていました。だから、小学校のときとか確か文集に、将来の夢は映画監督とか書いてましたね。
ただ、そのあと、現実を知って高校ぐらいになると「なれるわけないやんか」と(苦笑)。で、チャレンジもせず、普通に就職したんですけど、30歳を前にしたときに、「自分のやりたいこともやらないでこのまま死んでいいのか」とか考えちゃうわけです。
それで、夜間部なら働きながら通えるということで、ビジュアルアーツ専門学校大阪に入って、遅れてきた青春みたいな感じで映画を学びはじめたら、やっぱりこの道だと。
でも、そのあとも実はウジウジしていて。ビジュアルアーツを卒業後、助監督とかチョロチョロやってましたけど、自分の作品はしばらく着手できなかった。
で6~7年して、もういいかげんやらなということで2016年からようやく短編を作り始めた。
映画を始めたのも遅ければ、映画を作り始めたのも遅い、今もなんでもっと早くから撮らんかったんやと後悔ばっかりです(笑)。
——最後、もう映画で行こうと踏み出せたきっかけは?
ビジュアルアーツの先生が小谷忠典監督で。僕は生徒なんですけど、30歳ですから年が1つか2つしか変わらなかったんです。そんなんで可愛がってくれて、卒業後もよく飲みの席に呼んでもらったりしてたんです。そこで「映画をやるかやらんかはっきりせえ」とか怒られたりとか。
で小谷さんがドキュメンタリー映画『フリーダ・カーロの遺品』の制作にとりかかったとき、海外ロケに1カ月いくから、いっしょにくるかこないか決めろと。いくなら仕事辞めないといけない。最終的に、最後のチャンスかもと思っていったんですね。この経験が大きかった気がします。そのロケの1カ月、というか行きの飛行機で小谷さんと一緒になってから、帰国するまで、ずっと映画のことだけを考えっぱなし。撮影は確かにきつかったんですけど、映画に純粋に向き合い続けることができて、なにか自分が映画と同化していくような気分ですごい満たされた。なんか振り返ると、映画作りのだいご味を教えられた気がする。この経験が「映画やるぞ」と心を定めさせてくれたかもしれません。
——今回の入選はどう受け止めていらっしゃいますか?
SKIPシティには思い入れがあるんですよ。まず、助監督を務めた『見栄を張る』が2016年の本映画祭の国際コンペティションに入選して、受賞もした。それで、昨年『未来は未定』で優秀作品賞を獲ることがことができた。そして今回は、長編で映画祭に再び帰ってくることができた。ようやく真の意味での映画監督としてのスタートラインに立てたかなと思っています。
(取材・文:水上賢治)