ニュース
【インタビュー】『お笑えない芸人』西田祐香監督
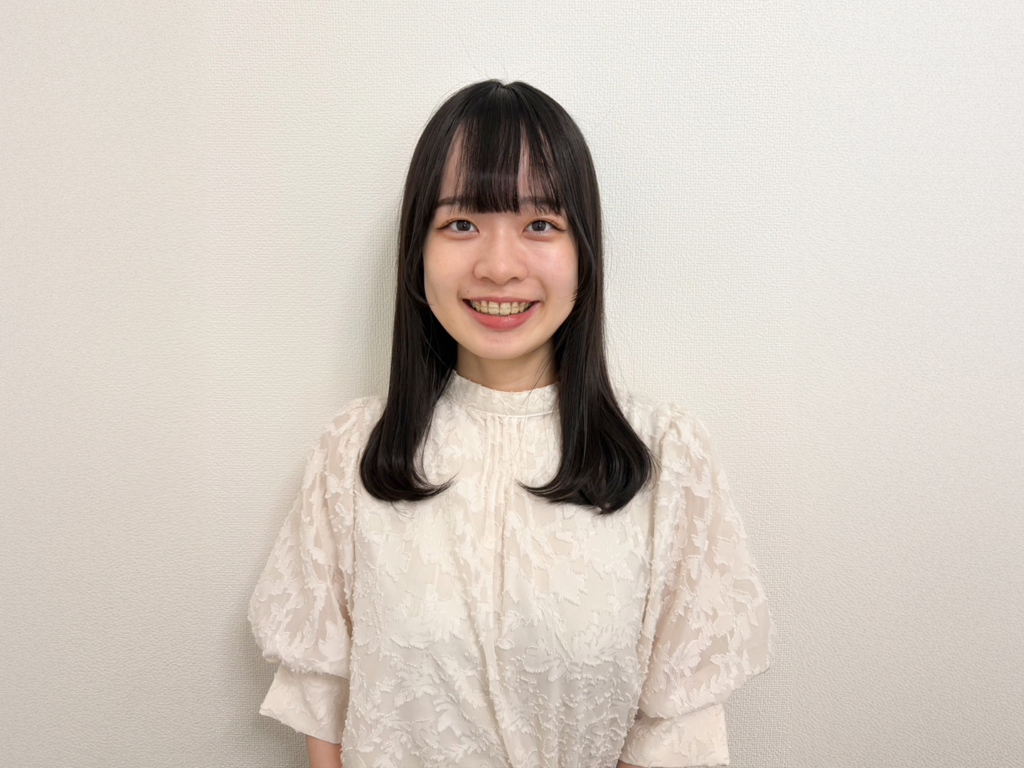
――いま若い才能を次々と輩出している京都芸術大学映画学科出身。この『お笑えない芸人』は、同大学の卒業制作作品になります。西田監督は大学では主にシナリオを専攻していたとのこと。たとえば、卒業制作では『このテーマの脚本を』『この温めてきた脚本を』みたいなものはあったのでしょうか?
「実は『お笑えない芸人』の脚本は大学三年生のときに書いたものになります。脚本もしくは論文を書くゼミがあって、そのときに書いた脚本です。当初、卒業制作は別のシナリオを新たに書こうと思っていました。ところが、担当教員の先生から『この脚本、卒制にしないの?』と言われたことで、『した方がいいのか?』と思い直し、卒業制作として取り組もうと心が動きました。周りに映画に情熱を注ぐ同期がいっぱいいたので、『みんなと形にしたい』という思いもありました」
――大学三年のときに書いた脚本をそのまま使用した形ですか?
「いえ、予算や時間に限りがあるので、たとえばロケ場所を変更したり、登場人物のキャラクターを変えたりはありました。ただ、基本となるストーリーラインは変わっていないです」
――芸人を主人公にした物語は、どのようなアイデアから生まれたのでしょう?
「2つの軸となるアイデアがありました。ひとつは、『芸人さんが万引きをしてしまって解散する』という設定でした。信頼している相方が万引きしていることを知ったら、主人公はどう思うんだろう、と。それで、そのようなシーンのあるものを描きたいと思いました。
もうひとつは『自己肯定感』をテーマにした物語を描きたい気持ちがありました。私はものすごくネガティヴ思考で自己肯定感が低い。ただ、話してみると、けっこう周りの人たちも同じで、自己肯定感が高い人にあまり出会わない。まぁ、わたしの周りだけかもしれないのですが……(苦笑)。なので、『なんでこんなにわたしたちは自己肯定感が低いんだろう』という思いをずっと抱いていて、そのことを描きたい気持ちがありました。この二つのアイデアを組み合わせて書き上げました」
――もともと大学でシナリオ専攻だったわけですけど、卒業制作ではほかの誰かではなく自分で監督をしようと当初から考えていたのでしょうか?
「はい。自分の生み出した世界は、自分で描きたい気持ちがあって、当初から監督も自分が務めようと思っていました。ほかの誰かに監督を頼むことは考えていなかったですね」
 ©映画「お笑えない芸人」製作
©映画「お笑えない芸人」製作
――物語は、お笑い芸人を目指す佐原が主人公。彼は瀬戸口という相方を見つけて「激甘酢豚」というコンビを組む。しかし、ある出来事でコンビはあっけなく解散となってしまう。するとその挫折からか、それともまだある自信からか、佐原の前に、“芸人として爆発的に売れた理想の自分”が出現。その分身が人生に介入してきて佐原は混乱していきます。その彼の姿から理想とは程遠い人生を送る人間のもどかしさ、あがき、恐れといった本心が浮かび上がってきます。
「まだそこまで長く生きてきたわけではないですけど、人生ってほんとうにうまく嚙み合わない。ままならないことだらけ。わたしもこれまで高校時代に不登校になるなど、噛み合わない時期を何度も経験してきました。たぶん誰しもがこういう時期を経験しているのではないでしょうか?そのことが物語には反映されていると思います」
――佐原の地団太を踏むような日々が痛切に伝わってきます。ただ、佐原を、たとえば『そこまで悩むなら芸人諦めたら』といったように突き放してはいません。切り捨ててはいない。むしろ、それでも芸人の夢に執着する佐原にエールを送るような物語になっている気がしました。それは、西田監督が公式サイトに寄せた「弱い人、というのは存在しないと思います。世の中が強すぎるだけです」というメッセージに通じます。
「甘いと言われればそれまでですけど、いまの社会はぜんぜん優しくないと感じます。ほんとうに元気100%で仕事と私生活がかみ合って生きている人が基準の世界になっているように感じる瞬間があります。たとえば体調を崩してしまうと、たちまち社会から置いていかれた気持ちになってしまう。瞬く間に取り残された気分になってしまう。もう少し弱い立場に置かれてしまった人が基準となる社会になれば、生きやすい社会になるのではないかと思います。ですから、佐原の存在をもちろんわたしは肯定していますし、佐原のように理想と現実が噛み合わないけれども、それでも一生懸命に毎日を生きている人たちにこの映画が届いてくれたらと思っています」
――佐原役の吉野真生さんがすばらしい。お笑い芸人というだけでもかなりのハードルが高い役。それをこなしながら、現実の佐原と空想上の理想の佐原という一人二役の難役を見事に演じ分けています。
「吉野は京都芸術大学の同期です。実は、相方の瀬戸口役の村山(暁)も同期で、二人とももともと映画の作り手を目指しているようでした。でも、大学三年生ぐらいから俳優の方にシフトしていった感じがあって、私は二人の演技に触れるたびにすごい才能があると思っていました。
だから、この作品に取り掛かることが決まったら、自分から二人に声をかけました。『出演してほしい』と。
佐原役に関しては、もう吉野以外はあまり考えられなかったですね。なんとなく佐原の人物像が明確になったとき、吉野に似ているなと思ったんです。ふだんは冗談飛ばしてばかりいるんだけど、裏では人知れず悩んでいるみたいなところが。本人は否定するかもしれないのですが。それで彼にお願いしたいと思いました。
実際演じるのは大変だったと思います。現実の佐原と理想の佐原が同画面に登場するシーンは、現実の佐原だけの映像と理想の佐原だけを撮った映像を二つ合わせる形になる。となると撮影の都合上、現実の佐原を撮って、次に理想の佐原を撮るといったように、どうしても交互に撮っていくことになる。俳優側は現実の佐原を演じたら、はい、次は理想の佐原になってみたいなことになるので大変だったと思います。でも、わりと本人は楽しんで演じているように私の目には映りました。吉野本人がどのようにスイッチを入れ替えていたのかわからないですけど、現場で見ていて現実の佐原のときと、理想の佐原のときとではガラッと印象がかわるのでびっくりしました」
 ©映画「お笑えない芸人」製作
©映画「お笑えない芸人」製作
――では、少しプロフィールについて伺いたいのですが、京都芸術大学映画学科に進むことになったきっかけは?
「もともと京都芸術大学の附属高校に進んでいて、そこに映画制作同好会があったんです。そこに所属して高校時代から、遊び感覚で映画を作って楽しい日々を過ごしていました。その流れで、絵が好きだから美術大学に進むぐらいの感覚で、京都芸術大学映画学科に進むことにしました」
――高校に進むまではそれほど映画には興味はなかった?
「漠然と映像を作ることに対して魅力は感じていて。自分で作ってみたい気持ちがありました。映像ってずっと残り続けるものじゃないですか?自分が作ったものが残り続けるって素敵だなと中学生ぐらいから思っていました。
それで高校で映画制作同好会に入って、映画作りの楽しさにはまっていきましたね」
――大学に進んで、自分の書いたシナリオを自分で映画化して、大学最後の卒業制作作品が入選です。知らせを受けたときはどんな気持ちに?
「めちゃくちゃうれしかったです。社会人になってちょうど自己肯定感が下がりかけた時だったので、その知らせをきいて一筋の光が見えたというか。自分がひとつ認められた気がしました。それから、やはりいろいろな方に見ていただけるチャンスができたのはすごくありがたいです。卒業制作展での上映後に、ありがたいことに『もう1回みたいです』とか『どこかで劇場公開されないんですか?』といった声をいくつかいただいたので、届けられるいい機会ができてよかったです」
――シナリオ専攻だったということでやはり主としてはこれからも脚本を書き続けていきたい?
「そうですね。書きたいです。いまは別の仕事をしているのですが、働けば働くほど脚本を書きたい意欲がふつふつとわいてきます」
――「こういう題材やテーマの脚本を書きたい」といったものはありますか?
「今回の『お笑えない芸人』と同じで、まずは人間をきちんと描きたい。その人物の表の顔も裏の顔も見えてくるような人間臭い物語をまだまだ書きたいです。それから、『お笑えない芸人』に込めた思いでもありますけど、弱い立場にいる人たちに向けた物語を書いていきたいです。世の中が強すぎるだけだと思うので、そこから追いやられて生き辛さを抱えた人たちがちょっとでも生きやすく心が安らげるような物語を届けたいです。そして、弱い立場にいる人たちにずっと寄り添い続けられたらという思いがあります」
『お笑えない芸人』作品詳細
取材・文:水上賢治




