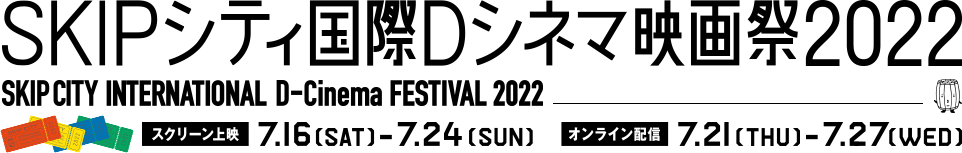ニュース
【インタビュー】国内コンペティション長編部門『明ける夜に』堀内友貴監督

――『明ける夜に』の話に入る前に、2021年に脚本と監督を手掛けて発表している『また春が来やがって』について聞きたいと思います。というのも、主要スタッフや出演者も『明ける夜に』と重なっているところが多く、どういう経緯で集まって映画作りを始めたのかを始めにきかせていただければと。
お察しのように、『また春が来やがって』と『明ける夜に』は、つながりがあります。どちらも東放学園映画専門学校映画制作科の在学中に完成させた作品になります。すべてのはじまりは『また春が来やがって』で。
専門学校に進んだものの、ご存知のように、コロナ禍で授業の一環として実際に撮影しての作品作りがほとんどできなかった。でも、僕としてはなにか作品を撮りたい。当時、僕と同じようなことを考えていた学生のメンバーが集まって作ったのが『また春が来やがって』でした。
あまり外にみせることとか考えないで、ほんとうに映画を作りたい気持ちがある学生のスタッフと役者たちの思いだけで作ったような作品だったんですけど、うれしいことに第32回東京学生映画祭で観客賞と審査員特別賞(城定秀夫監督)を受賞することができました。
それに味をしめたというわけではないんですけど、次への意欲につながって、すぐに「最後の夏休みにもう1本作ろう」という話になりました。「自主映画でももう少し規模の大きいものを」と考えて、クラウドファンディングで制作資金を募ったのですが、東京学生映画祭で知り合った今泉力哉監督からいただいたコメントなどが後押ししてくれて、無事に目標額をクリア。こうして新たに制作した映画が今回の『明ける夜に』になります。
――どういうアイデアから始まったのですか?
当時、僕自身の問題なのですが「モラトリアムからの卒業」みたいなことをずっと考えていました。いまのような学生気分が抜けないままではまずい、そろそろ社会人として進まないといけないなという時期で。モラトリアムの終わりのような物語を作って、自分自身もモラトリアムから抜け出そうとみたいなことを考えてしました。
ただ、全然、いいアイデアが浮かばない。ずっと書きあぐねていたんですけど、あるとき、撮影の中村(元彦)くんと話しているとき、春、秋、冬は何月何日で終わりという感覚がないけど、「夏だけは明確に8月31日で終わりって感覚があるよね」という話になり、「その日1日(8月31日)だけの群像劇とかおもしろいかも」となって、そこから脚本作りが一気に動き始めました。
――8月31日~明朝の9月1日までの物語で。予定していた面接が急遽延期になった就活生の山ノ辺とキミ。高校時代、野球部のマネージャーだった凛子に電話をかけて直接会う時間を迫る秀一。コンビニでバイト中の健斗とキョーコという3つの一晩の物語が海辺の街で進展していきます。いわゆる群像劇のスタイルで、まったく関係ないと思われていたこの3つのエピソードが徐々に近づいていきます。いくつかの物語をパラレルに進行させていきながら、ひとつにつむぎあげていく群像劇を作るのは難しいと思うのですが、トライしたい気持ちがあったのでしょうか?
そうですね。さきほど言ったように「群像劇とかおもしろいかも」となったとき、これまで書いたことがなかったので、「一度挑戦してみたいな」と思いました。その時点では、あまり深く考えていなくて、のちのち「群像劇って難しい!」と大いに悩むことになるんですけど(苦笑)。
脚本を書きあげる上で大きなポイントになったのは、キミ役を演じている花純あやのさんとの出会い。ちょうど脚本に書こうとしているときに、学校の授業で出会ったんですけど、彼女は大阪出身で関西弁ですごく印象に残った。
授業の後に、みんなでごはんを食べにいこうとなったんですけど、なんかお店に行かずにコンビニでお弁当を買って、みんなで食べるみたいなことになった。そのとき、僕に初対面なのに「化粧落とし買ってメイク落としていい?」と聞いてきて、こっちも「やだ」とかいえないじゃないですか。だから、「どうぞ」といったら、目の前で落として「ああすっきりした」とか言っている。
作品をみていただければわかると思うんですけど、山野辺とキミのエピソードにほぼ落とし込んでいるようなことになった。そのなんか自由で天真爛漫な感じがすごく印象に残って、花純さんがそのままの姿で出てもらえるようなエピソードを書けないかなと思ったんです。だから、花純さんにインスパイアされて山野辺とキミのエピソードがまず生まれた。
それから、コンビニでバイトしている健斗とキョーコのエピソードに関してはもともとアイデアとしてもっていたもので、夏の終わりにやはり恋愛が欠かせないかなと思って盛り込もうと思いました。
野球部のマネージャーだった凛子と野球部員だった秀一のエピソードに関しては、秀一を演じている奈良原(大泰)さんがきっかけで。奈良原さんとの出会いは、学校の授業でワークショップを見学する機会があって、そこに奈良原さんが参加していて知り合って。その後、いい役者さんだなと思って『また春が来やがって』で主演を務めていただいたんです。
その中で、僕の中で、奈良原さん坊主頭なので、どこかで「野球部の学生を演じさせたい」との思いがあって、このエピソードが出来上がりました。この3つのエピソードができて、うまく流れができるように組み立てていった感じです。
――いまのお話をきいていると、かなり出演されている役者さんたちから得たものを役に反映させているところがありそうですね?
そうですね。凛子役のとしお(理歩)さんも、すごく透明感があって、なんか「包丁を持たせたい!」と思って、ああいうことになったんです。振り返ると、役者さんの魅力にずいぶんと脚本を書く上では助けられたなと思います。
――あと、おそらく見た人は全員気になる、謎の男のアイデアはどこから(笑)?
それが、どこからアイデアが出てきたのか覚えていないんですよ。あるときに、「砂浜に埋まっている人がいたらおもしろいな」と思ったんですけど……。なぜ、あのような突飛な人物を思いついたのか、自分でも不明です(苦笑)。
――群像劇は脚本も大変だったと思うのですが、撮影も大変だったのでは?
真鶴での撮影だったのですが、コロナ禍ということで連日泊まりでとはいかず、その都度、車でスタッフとキャストを送迎しての撮影で。しかも夕方から翌朝の物語なので、実際の撮影もその時間帯でするしかない。午後から朝までの撮影でヘロヘロになってました。
しかも、9月の撮影で台風シーズンで天気とにらめっこのようなところも多々あり、心身ともに疲れ果てて、しまいには食事も喉を通らなくなって、10キロぐらい痩せました(苦笑)。監督で先導しなければいけない立場なのに、みんなから「大丈夫か」と心配されていました。いまはようやく元の体重に戻って元気です。
――そうした苦労を経て完成した作品が入選したという報せを受けたときの心境は?
めちゃくちゃ驚きました。SKIPシティは大きな映画祭なので、応募したもののまず無理だろうなと思っていました。(入選の連絡は)ちょうど実家に帰っているタイミングで、お昼ぐらいからめちゃくちゃお酒を飲んでいて酔っぱらっていたんです。よく映画やドラマで、びっくりすると急に酔いが冷めてシャキッとしてテキパキと行動をし始めるシーンがあるじゃないですか。そういう場面を見るたびに「またまた、絶対そんな急に酔いが冷めることなんてありえないよ」とずっと思っていたんです。
でも、実際に自分の身に起きたら、あまりの驚きに一気に酔いが冷めて(笑)、そこから携わってくれた仲間とかいろいろな人に一気に連絡を入れました。「ほんとうに人間びっくりすると、酔いが冷めるんだ」と身をもって体感しました(笑)。
あとは、やはり映画祭で入選したということは、少なくとも見てくれた方がいて、その外部の人が作品として認めてくれたということ。自分たちが作った作品が伝わるものになっていたということで安心したところもありました。
連絡を入れたら役者さんたちもスタッフもすごく喜んでくれて、みんなで「いろいろな映画祭に行けたらいいね」と話していたので、まずひとつその目標をクリアできたかなと思いました。

©堀内友貴
――ここからは映画監督を目指したきっかけなどをうかがいたいのですが、大学卒業後に東放学園映画専門学校映画制作科に進まれています。どうしてこういう経緯になったのですか?
映画は漠然とですけど好きで、よく見てはいたんです。両親が映画が好きでWOWOWに加入していて、食事のときは常にテレビから映画が流れているような家庭でした。
ただ、映画監督はあまり考えていなかったというか。ちょっとお恥ずかしい話なのですが、自我に目覚めたのが20歳ぐらいからで。それまではあまり、あれをやってみたいとか、これに挑戦してみたい、といったものがなかったんです。
ということで、とりあえず大学に進学したんですけど、在学中に映画を撮りたい気持ちが芽生えてきた。それで、山下敦弘監督が大好きで、出身大学の大阪芸大に転入したいと思ったんです。ただ、そんな勝手を親が許すわけもなく、「とりあえず大学を出てから考えなさい」といわれ……。
それでも諦めきれなくて、大学卒業後、映画の専門学校に2年間だけいかせてくれないかと頼み込んで、東放学園映画専門学校映画制作科に進みました。
――影響を受けている監督は?
いま名前をあげた山下監督、あと沖田修一監督、今泉力哉監督とかはめちゃくちゃ影響を受けていると思います。
実は、東京学生映画祭で今泉監督に出会ったとお話ししましたけど、今回の『明ける夜に』もダメもとで読んでもらえないかと思って、今泉監督に第一稿を送ったんです。
ありがたいことにいろいろとアドバイスをいただくことができたんですけど、直後に返ってきたメールにこう書いてありました。「僕の書く脚本に似ているね」と。今泉監督の『街の上で』の脚本を読みながら書き進めていたりしたので、意識下でめちゃめちゃ影響を受けていたんだろうなと思いました。
――どうですか、モラトリアムからは脱却できましたか?
いや、正直なところ、まだ抜け出せていないです。
学校卒業して、また自主映画を作りたいなと思って、脚本を練っているんですけど、思い浮かぶのは、年齢層がちょっとあがった20代半ばぐらいのモラトリアムにはまっているエピソードばかりで。まだ終われないのかなといま感じています。もしかしたら、僕自身の永遠のテーマにもなるのかなと最近感じています。
――といいながら、最近、劇団を立ち上げたりと新たなアクションを起こしているとお聞きしました。
何度か話にでてきた出演者の奈良原さんが舞台を中心に活躍されていて、「一緒にどう」と誘ってくださって、共同で立ち上げることになりました。「劇団セビロデクンフーズ」という劇団を5月1日に立ち上げて、6月に初公演をしました。ここでもいろいろな作品を発表していこうと思っています。
――どういう作品を作っていきたいと。
変に小難しくない、多くの人が楽しめる作品を作っていきたいと思っています。今回の『明ける夜に』も肩ひじ張らずにみてもらえる作品になっていると思っていますので、いろいろな方にみてもらえたらうれしいです。
『明ける夜に』作品詳細
取材・写真・文:水上賢治