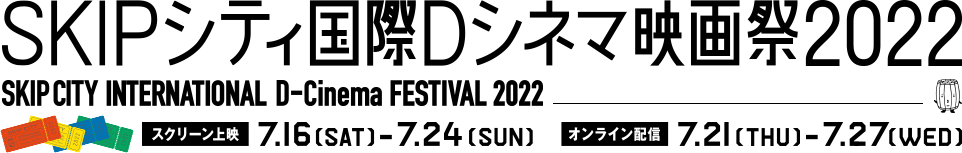ニュース
【インタビュー】国内コンペティション長編部門『ヴァタ ~箱あるいは体~』亀井岳監督

――全編をマダガスカルで撮影という珍しい作品で。実は、前作『ギターマダガスカル』もマダガスカルで撮影されていて、そのとき体験したことが今回の『ヴァタ~箱あるいは体~』の構想へつながったということですが?
はい、前作の『ギターマダガスカル』(2014年)は、マダガスカルの人々の営みと音楽を主題にしたロードムービーで。マダガスカルの4人の音楽家が自身のルーツをたどる旅に出る。その旅を記録したドキュメンタリー・ドラマなんですけど、彼らが向かう先の中には限りなく人のいないエリアもあるんですよ(笑)。車で道を走っていても、ほとんど誰にも会わないことがある。
だから、誰もいないところで急に人をみかけると、やっぱり気になって声をかけたくなるじゃないですか。で、前作の撮影時、マダガスカル南東部で箱を運んでいるグループに遭遇して、通訳を介してちょっと話を訊いたんです。すると、『死者の骨をその人物の生まれ故郷に運んでいる』と。
マダガスカルは生まれた土地を大切にすることは知っていたんです。国歌も訳すと『我が故郷』といったタイトルで、死んだら生まれたところに戻してほしいというのがマダガスカル人の基本的な願いです。外国で仕事していてそこで亡くなっても遺体は必ずマダガスカルに戻すといったような話もよく聞くことではあったんですね。ただ、死者の骨を担いで運び、生まれ故郷に戻すことは知りませんでした。
「ファマディアナ」といって、4~5年に1度、お墓から先祖の亡骸を出して、巻いてある布を新しいものにかえる儀式はみたことがあったんですけど、亡骸を運ぶ人たちをみたのはそのときが初めてでした。
――このときの体験が今回の作品へつながっていった。
そうですね。長く続く風習ですから、マダガスカル人にとってはなにも珍しいことではない。ただ、日本人の僕からするといまもこういう風習があることは、なぜかわからないですけど、心にひっかかるところがあった。頭から離れないので、2016年に再び同じ場所を訪れて、この体験をもとに新たな作品を作ることを心に決めました。
――そこからリサーチをはじめて、脚本を書きあげていった流れですか?
ええ、調べると、お金に余裕のある層は、亡くなったらすぐに遺体を棺に入れて、車で運びます。これはちょくちょくみたことがあったんですよ。そうではない、お金にあまり余裕がない層の人たちは、車代を出せないので、土葬してある程度の大きさになってから運ぶ。マダガスカルは乾季と雨季があるんですけど、農業が閑散期になる乾季に運ばれることが多いようです。そうした事項を踏まえて脚本を書きあげていきました。
――作品は、マダガスカル南東部の小さな村で暮らす少年・タンテリが、長老から出稼ぎの地で亡くなった姉のニリナの遺骨を持ち帰って来るよう伝えられる。その命を受けた彼が、3人の男とともにニリナの骨を故郷へ戻す。その旅路が描かれます。
ストーリーはあえてシンプルにして、このマダガスカルに残る風習をきちんと伝えるものにしたいと考えました。そこに前作の『ギターマダガスカル』に続いて、音楽と記憶というテーマも盛り込めればなと。というのも、実は、死んだら必ず生まれ故郷に還るということと、音楽と記憶というのがマダガスカルの人々の中において密接につながっていると僕は感じたんです。常々、僕は『音楽』ってなんなんだろうと、なんで人の心を惹きつけるんだろうと、考えているんですけど、やはり誰かとつながるからではないかと思うんです。誰かとなにかを共有できる、同じ思いになれたりするのが音楽の魅力で力なのかなと。
で、マダガスカル人に『あなたにとって音楽はどういうものですか?』と聞くと、多くがこう答えるんです。『祖先とつながるツールでしょ』と。もちろんマダガスカルにもプロのミュージシャンがいて、ビジネスの側面はある。でも、基本は音楽が祖先とつながるものという考えがある。だからか、マダガスカルでは伝統的な音楽とポピュラーミュージックがすごく近い。日本だと、伝統的な音楽といまのヒットチャートをにぎわすような曲になにか関連を見出すことは難しいじゃないですか。でも、マダガスカルは昔から伝わっている曲をベースにした、いまのポピュラーミュージックみたいな曲がいっぱいある。
マダガスカルのミュージシャンの曲を聞いていて、『なんかこの曲の感じ、聞き覚えがあるな』と思ったら、葬儀儀礼とかでよく使われるトラディショナルなフレーズだったりするんですよ(笑)。このマダガスカルの音楽と、この骨を故郷へ戻す風習はどこか相通じるところがあり、音楽自体の原点を感じるところもある。そういうことも感じられる作品になればと考えました。
あと、記憶についていうと、マダガスカルの人々は決して物資に恵まれているとはいえない。毎日なにかしら捨てる東京の生活とは大違い。ただ、別の豊かさがあるんですよ。その豊かさはどこからきているかというと記憶のような気が僕はするんです。マダガスカルの人々はいろいろな記憶を語り合うことによって、心にきちんと思い出としてとどめて、それを自身のアイデンティティや歴史として刻んでいる。先祖とも未来とも自分はつながっていて、自分は歴史の一部と感じられるようなものとして、自然と記憶を大切にして生きている感じがあるんです。なんかその記憶や思い出の大切さやすばらしさも感じてもらえたらなと考えたところがありました。
――マダガスカルというと日本ではあまりなじみのない人がほとんどだと思うのですが、作品を通して描かれている、この骨を運ぶ風習もそうですし、祖先を敬うところなど、日本にも通じるところがありますね?
マダガスカルの人々は、諸説あるんですけど、1500年ぐらい前にインドネシアやフィリピンからわたってきた人たちが祖といわれている。つまりアジアにルーツがある。そして、人生は永遠に続くと考えられている。死はひとつの区切りに過ぎない、死んだあとは祖先になるといった考えがあるんです。死んだら先祖や仏さんになるといった日本の考えとあまりかわらないところがあるんですよ。さきほど、音楽は祖先と交流するものという考えがマダガスカルにはあるといいましたけど、よくよく考えると、日本の盆踊りももともとはそうですよね。祖先を迎え入れる儀式だった。そういうことを考えるとちょっと親近感がわきますよね。
――あと、霊の存在の考え方も日本とわりと近いですよね?
幽霊の概念があるんです。「ルル」っていうんですけど、ルルをみたという人がけっこういる。あと映画にも登場しますけど、ルナキは祖先との祭事をつかさどる存在で。映画で描かれているのは、寝て夢の中で、祖先とつながることができる。夢以外にもつながる方法はいくつもあるでしょう。
あと、これも映画に登場していますけど、コーヒーの実を取る人のような、祖先と現実の狭間にいるような存在も考えとしてあるんです。それから、日本でいうところのイタコのような、霊を憑依させて話をする人もいます。
――こうした物語を全編、マダガスカル現地で撮影して完成させたわけですが、マダガスカルでの撮影がどういうものなのか想像できません(笑)。
そうですよね。当時はマダガスカルに映画館がなくて、僕の知る限り、マダガスカルで作られた劇場公開のための長編映画というのは2本で。1本はフランス人の監督が作っていて、僕の前作『ギターマダガスカル』がもう一本なんですよ。だから、映画体験をまったくしていない人もいるので、田舎にいくとそもそも『映画ってなんだ』というところから始めなければいけなかったりします。
ただ、今回は前作を踏まえて現地スタッフも集めたりしたので、そういう心配はなかったですね。脚本も現地の人々にどう感じられるかなと思ったのですが、基本的に彼らからしたら日常のことを描いているので、クビをひねられることはなかったです。むしろ、『外国人が考えたストーリーとは思えないぐらい、俺らのことをきちんわかっている』と言われました。『マダガスカルの世界観をきちんと描けている』と。
――出演者の方々はどうやって見つけたのでしょうか?
実は、前作『ギターマダガスカル』に続いて、ミュージシャン中心で。前作に続いて出演してもらっている方もいます。マダガスカルは日本に比べて、音楽が日常にあふれている国で、結婚式や葬式、ちょっとした祝い事など、なにかあるたびに楽団を呼んで演奏してもらうんです。彼らはプロミュージシャンかというと、そういうわけじゃなくて、農業をやりながら時間がある時に伝統的な音楽を演奏する楽団をやったりしている。マダガスカルの人々にとって音楽家は身近な存在なんです。ただ、それゆえにミュージシャンとして食っていくのは難しい。一握りのトップミュージシャンはくっていけるけど、そのほかは兼業なんです。だから常に仕事を探しているんで連絡はすぐつくんですよ。人を一人、二人挟めば確実にすぐつながる(笑)。会いたい人に会えますね。
今回の作品では、離れ小屋の男役のサミーは『タリク・サミー』というバンドでやっていて。僕は大好きなバンドで、この離れ小屋の男を誰にするかとなったとき、彼がいいなぁと思ってお願いしました。あと、レマニンジは前作に続いて出てくれて。タンテリとともに旅をする凸凹コンビのザカとスルも実は前作に少しだけ出演しています。彼らはトミノというミュージシャンのファミリーの一員で、『ギターマダガスカル』でトミノが家に帰ってきて演奏するシーンがあるんですけど、そこにザカとスルも出ていて一緒に演奏している。だから、キャストと作品に込めたテーマを含めると、僕の中では続編という意識もあります。
――もう原野ともいうべき雄大な自然の映像がほとんどで、撮影が大変だったのではと思ったのですが?
大変でした。まず、天気ですよね。ほとんどが屋外での撮影の映画なので、天候との闘いでした。乾季だったんですけど、雨が続いたりして、いやもう最後はあきらめて開き直るしかなかったですけど、撮影終わるか心配で心臓が止まりそうになりながら撮影していました(苦笑)。あと、骨を運ぶ人たちに南東部で会ったので、不便な南東部での撮影に決めたんですよ。いま振り返ると、利便性の高いもっと近くの場所でもよかったと思うんですけど(笑)。そこまで考えが及ばなくて南東部にしたんですけど、遠いんです。マダガスカルは淡路島ぐらいと思っている人がけっこういらっしゃるんですけど、実際は日本の1.7倍ぐらいあって広い。インフラが整っているわけではないから、道が非常に悪い。だから、東京から山口ぐらいの距離にいくのに、車で3~4日かかるんです。この移動は大変でした。
あと、山賊が出るエリアがあって。あるとき、複数の人とすれ違ったんですけど、スタッフが『いまの山賊だった』と。なにかあったときのことを考えて、警備を雇いました。それから、機材に関しても、差し出すものと、差し出しちゃいけないものを分けて撮影しましたね。

©FLYING IMAGE
――撮影がまたすばらしいのですが、小野里昌哉さんにお願いした経緯は? 写真家として活躍していると資料にはあったのですが?
大学の同期で、昔からの知り合いなんです。その通り、写真家として活動しているんですけど、映像をやり始めたというのを聞いて、お願いすることになりました。
――前作、今回とマダガスカルで映画を作られたわけですが、そのきっかけとなったマダガスカルの音楽との出会いはいつだったのでしょう?
1980年代後半ぐらいから、ワールド・ミュージックのブームがあって。当時、僕は高校生でバイトでお金貯めては中古レコード屋にいってレコードを買っていたんです。ただ、あんまりお金はない。で、いろいろな曲を聞きたいから、コンピレーションを買うこともあって、あるときに、イギリスのワールドミュージック・レーベルのGLOBE STYLEから発売になった「ワールド・ワイド・ユア・ガイド」というコンピレーション・アルバムを手にしました。そこにマダガスカルの楽曲が入っていた。おそらくそれがマダガスカル音楽との最初の出合いです。
同時期に、デヴィッド・リンドレイとヘンリー・カイザーいうアメリカのギタリストがマダガスカル音楽のコンピレーションのアルバムを出したんです。それがきっかけでマダガスカル音楽にハマりました。でも、当時、カセットに録音して友人らに聞かせたんですけど、誰一人としてハマらない(苦笑)。この良さをわかってほしい、彼らの音楽をちゃんときかせたい、その思いがマダガスカルでの映画作りへとつながっていったところがあります。
――映像制作自体はいつから始めたのでしょうか?
アートワークとしては彫刻から僕は始めていて、映画監督を目指していたわけではないんですよ。映像を作り始めたきっかけは、大学院を出た後で。能登半島で、中学の教員をちょっとだけしていた時期があったんですけど、そのときに、柔道場があって、布を使ったインスタレーションの作品を作ったんです。で、インスタレーションの作品なので、終わったら撤去なので、映像に残しておきたいと思って、デジタルビデオカメラで撮影した。それを編集してみたら、ちょっと手ごたえのようなものがあって、そこから短い映像作品を作り始めました。
その短い映像のインスタレーション作品がギャラリーとかで展示してもらえるようになったんですけど、こういう作品って基本的にどこからみてもよくて、映像の途中からみてもよくて、だいたい立ったままみるじゃないですか。そこが僕としては不満で、なんか最初から最後まで座ってみてほしいなと思ったんです。そうなるとそれは映画だろうということになり、『チャンドマニ 〜モンゴル ホーミーの源流へ〜』は映画として発表することになりました。だから、どこか今も映画の手法をつかったインスタレーションをやっている感覚もあるんです。
ただ、よくよく考えると、僕は高校時代、映画研究部で8ミリで映画を作っていたんですよ。すっかり忘れていたんですけど、『チャンドマニ 〜モンゴル ホーミーの源流へ〜』を完成させたときに思い出しました。なので、映画を作りたい気持ちは以前からあった気がします。
――今回の入選はどう受けとめていますか?
僕はあまり映画祭に応募していないんです。めんどくさがりで(苦笑)。ただ、初監督作の『チャンドマニ 〜モンゴル ホーミーの源流へ〜』に関しては、SKIPシティに応募したんです。でも落選でした。だから、今回もまあ、難しいだろうなと半ば諦め気味だったんです。それが入選しましたと連絡がきたので、びっくりしました。僕の中では、SKIPシティは、日本を代表する長編劇映画の、若手映画作家のための映画祭だと思っているので、若くもない僕の、しかもちょっと変わっている映画を、よくノミネートしてくれたと思います。いや、でもうれしかったです。
『ヴァタ ~箱あるいは体~』作品詳細
取材・写真・文:水上賢治