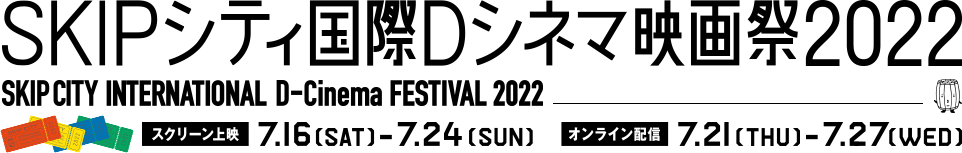ニュース
【インタビュー】国内コンペティション長編部門『命の満ち欠け』小関翔太監督、岸建太朗監督

(左から)小関翔太監督、岸建太朗監督
――『命の満ち欠け』は、薬物依存症の弟ユウサクと、彼を更生施設から家に連れ戻し、弟の人生を基に映画の脚本を執筆し始めた兄ショウタの物語。いつ足を踏み外してもおかしくない、ぎりぎりのところで「生」に踏みとどまっているような二人の愛憎が入り混じる関係が描かれます。小関さんがまさに自らの身を捧げたのではないだろうかということが想像できる作品です。どういうかたちではじまったのでしょうか。
小関:はじまりとしては、僕の大切な二人の友人の存在がありました。ひとりは僕が演じている弟のユウサクのモデルになっている友人で彼は実際に薬物依存になってしまった。
もうひとりはお弁当屋さんのミサトさんのモデルになっている友人で、その友人は若くしてオーバードーズで亡くなってしまいました。自然の力ではない、人間が作り出した「薬」という人工的なもので人生を壊滅させてしまう人を間近でみてしまった。
でも、どちらも僕はそばにいたのに何もできなかった。そのことがずっと心に引っかかっていました。そして薬物依存となった友人が、自立支援施設に入ったのですが、もう映画に描いたとおりで、ひどいところでした。
もちろんちゃんとした更生施設もあります。でも一方で、薬物依存の彼らのように行き場のない人間とその家族の弱みに付け込むというか。家族や周囲の人間としてはもう頼るしかないわけですけど、中には社会的弱者を抱えておくことで国から支援金をもらい、自分の懐を温めている人間がいる。
僕はその事実をダイレクトに目撃してしまった。そういう人間に対する怒りがまずは作品の出発点でした。
――そこから脚本を書き始めた?
小関:そうですね。
――岸監督とはどのタイミングで一緒にとなったのでしょう?
岸:いま話に出たひどい自立支援施設を運営するマツナガ役の伊藤慶徳さんと僕は知り合いで。慶徳さんと小関くんもまた知り合いでした。
慶徳さんは、小関くんにわりと企画の初期段階からマツナガ役の打診を受けていた。話の中で、小関くんが主演兼監督なので直感的に僕をイメージして推薦したそうです。1年半ぐらい前だったと記憶しています。
小関:実は慶徳さん以外にも、フジシマ役の梅田さんを始め、何人かに岸さんを推薦して頂いていました。僕も、岸さんが撮影した作品は何作か見たことがあって。その後『未来の記録』と『Hammock』など、岸さんの作品を見せて頂いたんですが、特に『未来の記録」には、ここでは感想を書ききれないくらい心を打たれてしまって…。
岸:小関くんと会っての第一印象は、というか、まず、その時点でのシナリオを見せてもらったんですけど、もう自分の人生の命を削って書いていることがわかった。そして、目の前にいる小関くんを見ると、「この映画を撮れたらもう俺は死んでもいい』みたいな顔をしている。
小関:友人が薬物依存になってなにもできなかった自分への怒りもありましたし、一方で彼が施設に入ったときいたとき、どこか安心している自分がいた。これで好転するのではないかと思って、大丈夫だろうと彼の存在をちょっと頭から消し去る自分がいた。でも、施設の実態はひどいもので……。どこか現実をみようとしなかった、友人ときちんと向き合おうとしなかったのではないかというや悔やみが残った。
それで、監督メッセージにも書いたんですけど、ユウサクを演じることで、友人が抱えていたであろう絶望や苦悩を実際に経験しようとすることで、頭で理解すること以上の「何か」に触れたいと思っていた。そういうことが顔に出ていたと思います。
岸:その顔をみたら、もう、断れないですよね。これはたぶん僕がやらなければいけないと思ったし、やるべきことなんだろうと思いました。でもきっと大変なことになることは目に見えていたので、自分も覚悟して挑まないといけないなと思いました。
――その時点での脚本から、岸監督はどんなことを感じたのでしょうか?
岸:最初にもらった脚本は、小関翔太の告白のような形式で、全てを撮影したら4時間を超えるような厚さがありました。私的な告白というか、叫びというか。さきほど小関くんが話したように、彼はユウサクを演じるということで、友人の苦しみを追体験しようとしていた。
それは、作品世界の中で、自分を傷つけて友人が味わったであろう苦悩を体験する。そのことでしか、小関くん自身の魂は救われない。そのことで、ようやく小関くん自身は友人と真正面から向き合える。そんなように僕の目には映りました。
それから、ユウサクはまるで世の中の苦悩をすべて背負おうとしているような人物で、それを小関翔太という俳優は自らの体で丸ごとひきうけて背負おうとしている。
それは、なにか十字架を背負うイエス・キリストの姿を想起させますし、と同時に、旧約聖書の一部をなす書であるヨブ記のヨブとイメージが重なったんです。
ヨブ記は不当な試練がテーマで,ヨブは自ら試練に巻き込まれて、その試練の意味を理解しようとする。そのことを思い返しながら、この映画のモチーフにヨブ記を敷くべきではないかと直感しました。
続けて、キリスト教文化の中にある、苦悩の中にしか救いはない、十字架を背負ったキリストの苦悩に救いをみようとすることが、この映画を通じて土台にすべき方向性なのではないかと思いました。そのことをひとつの提案として割と初期に話したと思います。
――この岸監督からの提案を受けて、小関監督としてはどんなことを考えたのでしょう。
小関:岸さんと出会う前までと、岸さんと出会ってからでだいぶ脚本はかわりました。というか、作品への向き合い方が変わったと思います。
そのとき、僕は自分自身にいろいろあって、この作品に向かうことでしか、生きていられない状況で。さきほど岸さんが言ったように、もう命を削って書いて、これを撮れたらあとはどうでもいい、死ぬ気で取り組んでいた。
また、それぐらい強い想いを示せば、監督としての実績もない、脚本家としてのキャリアもない、なんの信頼もない僕の作品でも、周りを動かして実現させることができるのではないかと考えていた。
この作品をできないと、僕自身、どうにもならないところに追い込まれていたんです。それを岸さんは見抜いていた。
で、さきほどのような話し合いがもたれたとき、少し冷静になれたというか。自分の思いを共有してもらえた気がして、この作品をどのような形にするのがベストなのか考える心の余裕ができた。
すると自然と、前提としては「ユウサクを演じ、友人が抱えていたであろう絶望や苦悩を実際に経験しようとすることで、頭で理解すること以上の何かに触れたい」というのはあるのだけれど、そこを経て、自分自身が生きていこうと思える気持ちになれるようなものにしたい、するべきではないかと思えた。
それまでは、「死んでもいい」とネガティブな方向だったのが、そこから意識がポジティブに切り替わったところがありました。
岸:はじめの脚本は、極端なことをいってしまえば全員が破滅してしまうような話だったんです。ただ、それだと負=悲劇みたいな短絡的な構図でしかなくてちょっともったいないなと僕は思ったんです。
たとえば、悲しみの中にある喜びだったり、死の中にも感じられる生みたいなことをくみとっていけば、もっと普遍的なものになるのではないかと思った。そういうことをひとつひとつ点検していく作業を半年ぐらい続けました。真剣な作業だったんですけど、おもしろかったですよ。
小関くんはやはり俳優なので、ある助言をすると、なにか自分の身体の中に言葉がおりてきて、それを一気に書く。それを僕が受けて、また話し合い、ときには演じる役者にも意見をきく。
小関:いやこのやりとりはすごくよかったです。
今後、映画を撮る場合も、この手法ならばかなり強いものを書けるんじゃないかと思いました。このおかげでこの映画で表現しようとしたことのサイズがアップした気がします。
――こうして作業の末に出来た脚本をもとに、撮影は始まったと思います。きわめて近しい人の話でもあり、自分に深く関わることでもある中で、描く上でなにか「これだけは」と大切にしたことあったでしょうか?
小関:友人が味わった苦しみや悲しみをまずはきちんと描くこと。
ただ、そうした破滅的な感情だけではなく、彼の中にもあるいい部分も目を向けて、自分にも肯定できる点があることに気づいてほしいというか。おそらく友人はこれまで誰からも称賛されるといった経験がなく生きてきたと思うんです。そんな彼が、「これだったら」と前をむけるもの。そう思えるものさえ残ればいいと思っていました。そして、願いとしては観てくださる方が友人に拍手を送ってくださるようなものになってくれたらと思いました。
――小関さんの魂の入った脚本があったわけですが、やはりそこに魂を入れるには俳優たちの存在が必要不可欠だったと思います。どの役も半端な気持ちでは引き受けられない人物だったと思いますが、もうみなさん小関さんの意を汲んでその人物としてそこに立っている。ひとりずつきいていきたいのですが、まずは小関さん、薬物依存症のユウサクを、ここまでの話からもわかるように身をなげうって演じられています。そうせざるをえなかったわけですが、演じるにあたってどういうことを考えていたのでしょうか?
小関:ひと言で表すと、「僕は絶対にブレてはいけない」という意識で臨んでいました。
ユウサクとしてそこに立っていればいい、そこにみんながぶつかってきてくれれば、僕はすべてに対してリアクションをとるし、すべての責任をとると思ってやっていました。シンプルにそれだけでいいと思いました。
逆に、それ以上のことを抱えてはダメだと思いました。あの人にはこう対応するとか、ここはこの人とのやりとりを踏まえてとかになるとダメだと思いました。とにかく、ユウサクとして立っていればいい。
これまでは、俳優としては自分のところだけを考えればよかった。でも、今回はすべて引き受けるとなったので、正直、はじめ大丈夫かなと思ったんです。
ただ、いざすべて引き受けると心に決めたら、もうやるしかないし、余計なことを考えるひまもない。失敗したらすべて自分の責任なので、変に言い訳せずに切り替えられる。だから、案外、楽でした。
俳優って繊細な生き物なので、自分がきちんと演じられているのか、このシーンはうまくいったのか、といちいち気になる。でも、そんなこと言ってられない状況に置くと、逆に楽で、やるべきことに集中できてよかったです。
――ユウサクの兄、ショウタ役の上原剛史さんもすごいですね。
小関:今回、メインでお願いしている役者さんたちは、僕が信頼している長い付き合いのある方ばかりです。というかこういう内容でまず理解してもらわないといけなし、演じ手としても信頼できる人でないと任せられないと思ったので。
上原剛史には、ほんとうに昔からよくしてもらっていて、僕のめんどうをずっとみてくれてきたような存在で。自分で言うのもなんなんですが、「上原剛史は小関翔太を絶対に見捨てない」と思えるぐらいの仲なんです。
ユウサクとショウタの兄弟の関係性を考えたとき、もう地続きでやらないと、お互いの苦悩にはたどりつけない、リンクしないとかなりきついことになる。そう考えたときに僕にとって兄として存在してくれるのは、上原剛史しか考えられなかった。
岸:彼じゃないとできなかったと思う。
それでも最初は不安で、半強制的に2カ月ぐらい前から小関くんの家に一緒に住んでもらうことにしました。今までの関係を、さらに本物の兄弟のようになるまで深めてもらおうと思って。でも、そこでできた関係性は、演じる上でもひとつ大きな力になったんじゃないかな。
それから、先ほど話に出てきましたけど、マツナガ役の伊藤慶徳さんも、悪人感が半端なかったです(笑)。伊藤さんの悪い顔は、この映画の大きな見どころかも知れません(笑)。
ただ、この映画はある意味「誰が悪なのか」、を問おうとする作品でもあって。その意味でマツナガは二重、三重と人物造形を深める必要があった。とても難しい役だったと思います。
――見ていただく方の楽しみを奪うようなのであえて詳細は控えますけど、フジシマを演じた梅田誠弘さんの異様さも際立ちます。
小関:いっしょにご飯にいったり、近所を散歩したりする仲だったりするんですけど、もともとはすごく穏やかでやわらかい感じなんです。けど、ふとした瞬間、あることに集中したとき、明らかに表情が変わる、存在がかわる。ものすごく珍しい人だなと思っていて。
フジシマは、ユウサクにとって崇拝する人物となりうる存在ですけど、それを考えたとき、もう梅田さんしかいないのではないかなと思いました。
イメージとしては、『ノーカントリー』でハビエル・バルデムが演じたアントン・シガーのような感じというのは伝えてあとは任せました。
それで出てきたのが、あの演技でびっくりしました。あの異様な迫力というか得体の知れない怖さには。ただ、本人は珍しく最初に弱音を吐いていたんですよ。「この役はどうすればいいのかわからない」とメールがきた。
でも、僕は「絶対にクリアしてくるんだろうな」と思っていました。案の定、とんでもないものを出してきた。あの梅田さんの芝居をみたときは、鳥肌が立ちました。
――もうひとり、ユウサクとショウタを見守るミサト役の加藤紗希さんは?
小関:お話ししたように亡くなった友人を投影しているのですが、むしろ生きていたとして描きたいと思ったんです。
ユウサクが抱えている苦悩に対して、変に同情するでもなく、妙に優しくするでもない。ごくごく普通の生活を送る生活者として、まっすぐにきちんと褒めてもくれれば指摘もしてくれる。そういう存在でしかユウサクを救うことはできないと思いました。
すでに亡くなってしまった故人ではありますけど、僕の中では生きているのでそうしたかったんです。

©2022 K-zone.LLC.
――いろいろと「あのシーン」はと聞きたくなるのですが、ひとつだけ、あの羽化したばかりのセミは、どうしたんですか?まさにタイトルの「命の満ち欠け」を象徴するような存在になってますが。
岸:「命の満ち欠け」というからには、「命」について何かしらを表す作品でなくてはなりません。
一方、僕らにとって「命」は余りにも自然すぎて、溢れていて、だからこそ、逆に見えにくい、感じにくいものでもあると思ったんです。では「命」をどう映画の中で見せるのか、感じさせることができるのか。その答えはなかなか出ませんでした。
そんなことを考えながら撮影を初めたのですが、撮影二日目の夜に、蝉の羽化が始まる前の幼虫を偶然発見しまして。そのあとは全ての予定をキャンセルして、羽化の撮影に集中しました。
小関:岸さんは何かに取り憑かれたみたいになって、4時間くらいぶっつづけで撮影していました。しかも何にも説明せずいきなり撮影を始めるから、演出部の人が怒ってました(笑)
だけど、蝉が僕の手の平に乗っかった時の不思議な感触は、未だに忘れられません。
岸:蝉の幼虫はまさに映画の神様からもたらされたギフトだと思いました。
そしてそのギフトを、映画の中のメインプロットに昇華することができたら、この映画はとても強いものになると思ったんです。だから撮影全体を通じてずっとそのことを考えていました。
――作り終えていまどういうことを感じていますか?
小関:少しお話ししたように、僕自身がいろいろとしんどいときにいて、はっきり言うと、ちょっと自暴自棄になっていたところがあったといま思っていて。
この作品を完成させて、この世界に生きる手がかりをみつけた気がしています。
岸:僕にも小関くんのように自殺してしまった友人が居て、そのことがきっかけで『未来の記録」を作ったので、小関くんが現れたときに、彼が抱えている苦悩がすっと伝わりました。
当時の僕には支えてくれる人がいましたけど、彼はそのとき誰もいない状態だった。だから、僕がやるしかないなと思ったし、これもなにかのご縁だと思ったんです。
僕はこの作品を作ることで、小関くんがいい方向にいってくれればと思ったし、もし薬物依存症の友人がこの映画を見たら、なにかいい方向に向かっていってくれたらと思っていました。
――ほんとうに魂を込めて作った作品だと思いますが、今回の入選の報せはどう受けとめていますか?岸監督は12年ぶりの入選になりますね?
岸:12年ぶりで、この深いご縁に感謝しています。SKIPシティには、2010年に監督作『未来の記録』で初めて参加して、ありがたいことに劇場公開のバックアップもしていただいたのですが、実はそれ以上のものをいただいているんです。
というのも、その後、ご一緒させてもらうことになる人たちの多くが『未来の記憶』がご縁で繋がっています。
たとえば、SKIPシティに入選した『Noise ノイズ』の松本優作監督も、『海辺の彼女たち』の藤元明緒監督も、『種をまく人』の竹内洋介監督も、『未来の記憶』とのご縁で僕が撮影監督をすることになりました。他にも僕は現在、撮影者として様々な方とご一緒させていただいてますが、SKIPシティが『未来の記録』を選んでくれていなかったら、そういうご縁はなかったかも知れない。
小関:これまで作品と向き合うときというのは、俳優なのでどうしても役者目線でみてしまうところがありました。
作品全体のことを深く考えてはいるんですけど、たとえばきちんと役を成立させられているのか、もうすこしできることがあったのではないかと、どうしても自分の演技に目がいってしまう。
ただ、今回、監督も兼ねているとなったとき、まったく見方が変わって、この作品が他者に届くものになっているのか、ものすごく不安になりました。まったく伝わらないものになっていないかと、もう不安でいっぱいになった。
だから、入選の報せを受けたときは、ひとつ安堵したというか。少なくともこの作品をみて、ここで描かれていること、ここに登場する人物たちのことを受けとめてくれる人がいたことに安心しましたし、この作品が描く世界に気をとめてくれる人がいることがうれしかったです。
――映画祭をどういう場にしたいですか?
岸:映画祭を通じて新たな出会いがあればと思いますし、とにかく『命の満ち欠け』を大きなスクリーンで上映してくださることに感謝します。またこの映画祭でしか見れない作品も多いので、できる限り多くの上映作品を見ておきたいです。
小関:そうですね、僕も映画祭はなにか出会いがあればなと思います。海外の監督もいらっしゃる予定とのことで、機会があればお話ししたいです。
岸:僕らの作品は、英語字幕に相当な日数をかけています。是非諸外国の方々にも見ていただきたいと思っています。
小関:海外の方がどう感じるのか、すごく知りたい。そうですね、国内外かかわらず感想をいただけたらうれしいです。
『命の満ち欠け』作品詳細
取材・写真・文:水上賢治