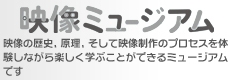【インタビュー】『マイマザーズアイズ』串田壮史監督

――『マイマザーズアイズ』の話に入る前に、長編デビュー作となった『写真の女』について少しお聞かせください。同作は<SKIPシティ国際Dシネマ映画祭2020>でSKIPシティアワードを受賞したほか、世界の映画祭で40冠に輝きました。世界の映画祭をめぐったこの経験はご自身にとってどういうものになったでしょうか?
コロナ禍ということで映画祭に実際現地を訪れることは叶いませんでした。ただ、その代わりオンラインでのQ&Aという形になることで、なかなか行くことが難しい映画祭にも参加できた。このことは自分としては大きな経験になりました。
『写真の女』は2020年の当時のレタッチ事情といいますか、インスタグラムをはじめとしたSNSでの写真のアップロードが広まっていって自身の写真を加工することが珍しくなくなった時代が色濃く作品に反映されています。
世界の映画祭での質疑応答も、そういった点のことを話す機会が多かった。その中で感じたのは、写真を加工することに抵抗がある国もあればない国もある。加工することに抵抗がある人もいれば、ない人もいるということ。『写真の女』は東京の大田区を舞台にしていますが、(写真加工をめぐって)大田区の片隅で起こったことと似たようなことが実はニューヨークでも起きている。ロンドンでも大差のないことが起こっている。そのことを実感しました。
もっと広い視野に立つと、映画というのは時代性が色濃く出て、それに対して世界の人々が共感する可能性がある=世界に届く可能性があるのだなと実感しました。
――その後、次回作へ向けてはどんなことを考えていたのでしょう?
実は、SKIPシティアワード(※SKIPシティにある彩の国ビジュアルプラザ内の映像制作支援施設及び設備を一定期間利用できる)を受賞したので、川口市で映画を撮ろうと当初は考えていました。僕自身、いま川口在住でもあるので、川口市をモチーフにした作品を作ろうと考えていたんです。
ちょうど企画を練り始めた昨年の3月ぐらいはそう考えていたのですが……。『写真の女』が北米にソフトの権利が売れていて、企画を練り始めていた前後にサンプルが送られてきたんです。で、ジャケットを見てみると、これが完全にホラー仕様。しかもけっこう好調だったんです。
つまりホラーのマーケットに入る作品だった。これは自分としても意外でした。ただ、振り返ると、一番最初に配給権に興味を示してくれた海外のバイヤーが『この映画にはマーケットがある』と言っていたんですよ。当時の僕は『何を言っているんだ?』と言った感じで終わったんですけど、おそらく彼は極東のホラー映画というジャンルには世界的なマーケットがあるという事を言ってくれていた。そのマーケットに「君の作品は入るんだよ」と伝えてくれていた。
そのことに気づいて次回作について少し考え直すことにしたんです。まだまだ無名の新人監督ですから、自分の特色を打ち出していかないといけないし、海外の方が見たときに『あの監督か』と引き続き興味をもってもらわないといけない。
――そこでじゃあ、ホラーというジャンル映画の特色をもっと強く打ち出してみようと?
そうですね。自分がジャンル映画の監督にはまるとは正直思ってもみなかった。でも、『写真の女』を少なくとも北米の方々はホラー映画として受け止めてみてくださった。ならば、作品としての一貫性と作家としての一貫性を出すにも、そのジャンル色をもっと強く出してもいいのかなと考えました。
――そういわれると確かに『写真の女』はカマキリの共食いシーンをはじめ残酷な場面がけっこうあって。かなり身体的な痛みを伴う映画になっている。そこを強調していくとホラーというのはなるほどと思います。
確かにそうなんです。で、少し考えました。自分はけっこう残酷なものに惹かれているところがあるんじゃないかと。
思い当たるのは、中学1年のときの体験。サッカーをしていて腕の骨を2本とも折ったときがあった。それで手術をしてボルトのようなものを入れてつなげたんです。そのボルトを入れるときは全身麻酔だったんですけど、抜くときは局部麻酔だった。抜くときは医者が『大丈夫』とのことで局部麻酔だったんですけど、麻酔がうまく効かなくて、あまりの激痛に大声で叫んでしまった。そのあと、叫びすぎて呼吸が苦しくなって、ちょっと収まってきたら、たぶん正気を保たないといけないという本能からか、あまりの痛さに逆に爆笑していたんです。あえて痛いと考えないようにからか、とにかく笑っていた。この体験がいまでも強烈な印象に残っている。ほんとうに痛いときって、笑うことで痛みをすり替えようとするんだなと思ったんですよね。痛い要素と笑いの要素というのは、ホラー映画に必要なこと。そう考えるとと、僕はホラーの素養があったのかもしれないと最近思い始めました。
――そういった中で、今回の脚本はどのように生まれてきたのでしょう?
『写真の女』を踏まえ、テクノロジーの進歩と、その技術革新によって自分が何者かわからなくなるという2点を引き続きのテーマとした上で、そこからさらに発展した物語を考えようと思いました。
――物語は、チェロ奏者の母・仁美と娘・エリが主人公。近年、映画でクローズアップされる機会の増えている母と娘を主人公にした理由はなにかあったでしょうか?
母と娘のリアルな関係性を描こうという考えはありませんでした。まずチェロのイメージが、出発点としてありました。チェロという楽器は視覚的な印象として、人間の大きさで、女性的なフォルムをしている。演奏しているところは母親が子どもを抱きしめているようにもみえれば、逆に子どもが母親に抱きついているようにも見える。そこから母と娘がチェロを二重奏しているイメージがわいてきた。
僕はチェロを演奏するわけではないので、そこからいろいろ調べていくと、チェロの音色というのは人間の声に最も近いといわれていることを知りました。高い音で弾くと叫んでいるように聴こえ、低いと唸っているように聴こえる。ホラー映画において大切な恐ろしい雰囲気を出すにはぴったりの楽器だと思いました(苦笑)。
ということでそこからいろいろとイメージしていまの物語ができていきました。
ただ、振り返ると、母と娘の関係に興味はあったといいますか。
これも両腕を骨折した(苦笑)中学校一年生の時でしたが、菅野美穂さんが主演を務めたTVドラマ「イグアナの娘」を見ていて、これが大きなインパクト大の映像体験でした。
この物語は、母親が娘がイグアナに見えてしまい、どうしても愛せない。もしかしたら、子どもを愛せない母親をきちんと描いた、しかも子どもがみる時間帯で放送した初めてのドラマだったかもしれない。僕の中にずっと強烈な体験として残っていた。そのことが今回、母と娘の関係を描くことへ僕を向かわせたところはあった気がします。

©2023 PYRAMID FILM INC.
――母子二人で幸せに生きてきた仁美とエリでしたが、ある日、母の仁美が車で事故を起こしてしまう。その事故によって仁美は視力を失い、娘のエリは重症で入院を余儀なくされるという不幸に見舞われる。そういう中で、視力を失った仁美はカメラ内蔵のコンタクトレンズを装着、病室のエリが装着するVRゴーグルとつなげることで二人はひとつの視覚を共有することになる。そこからはじめは母と子の日常を取り戻そうとしていただけの二人が微妙な関係に陥っていき、予想もしない事態が巻き起こります。ひとつの視覚を共有するカメラのアイデアはどこから?
先ほど少しお話ししたように、テクノロジーの進歩を引き続きのテーマに置きたかった。そこで考えをめぐらせていたとき、2020年代を生きている自分を含めた人々にとって何かを記録して残すデバイスはスマートフォンになっている。もはや単に自分の日常を記録するだけにとどまらず、あらゆる自分の情報がスマートフォンに集約されている。
かつて寺山修司は「わたしはわたし自身の記録です」と言った。つまり人間の性格やアイデンティティといったものは自身の記憶によってできていると。とすれば、もはや現代の人々にとって、スマホが自分そのものではないか。極端なことを言うと、スマホで自身の体験をすべて記録してしまえば、その映像が自分であって、その映像をそのまま誰かに渡してしまえばその人がわたしになるかもしれないのではないか。スマホの登場で記憶することがどんどん人間の脳から機械に移っていっている気がして、そういうことが起きてもおかしくないのではないかと考えました。
そのようなことを考えたとき、ふと思い出したのが15年前ぐらいに読んだある記事でした。仁美が装着するカメラ内蔵のコンタクトレンズというのは架空ではなくて実際にあります。僕は15年ぐらい前にその目に装着するカメラについて書かれた記事をたまたま目にして知りました。最初は義眼の人が自分の生活を記録するみたいなことで使い始めたようです。そこからいろいろな人が目の中にカメラを入れて記録していくことをしていて、いまはそのカメラがコンタクトレンズサイズになっている。近い将来、実用化されると思うんですけど、いずれにしても実際にある。
そういったことが結びついて、娘が母の映像を受信してみてはどうかというアイデアへ発展していきました。そして、ひとつの視覚を母と娘で共有したときに、二人の気持ちはどう変わるのかを、描けるのではないかと思いました。
――母の仁美と娘のエリは視覚を共有することで、お互いの本性があらわになってだんだん関係が逆転していきます。詳細は伏せますが関係はある意味、意外なところに着地します。
仁美は娘にいわれるままになる。となると、通常であれば怒りや憎しみといった方向に感情が向かっていくんでしょうけど、仁美はちょっと違う。むしろ真逆の感情が生まれてくる。でも、母であることが必要以上に求められる社会であると、仁美のような心情になってもおかしくはないかなと考えました。また、こんな考えに仁美がなってしまうのも、それはそれでホラーだなとも思いました。
――ホラーならではのシーンも随所にあります。中でもチェロを使った残虐シーンの2つはひとつの見どころです。
そうですね。僕は勝手に「腹びき」と「首びき」と命名しているんですけど、これはまだホラー映画史上で登場していない残虐シーンではないかと思っています。誰もみたことのないシーンになったのではと自負していて、初めてチェロを凶器に用いた映画かもしれないとも思っています。
ここだけの話、実際はあのように切れることはない。ただ、チェロの弾き方は、のこぎりで木を切る感じと同じような力の入れ方をしているそうです。そのことも知って凶器になって不思議ではないということで、あのような過激なシーンを作りました。

©2023 PYRAMID FILM INC.
――では、キャストに話を映しますが、まず母親の仁美役は、小野あかねさんは、どのような方なのでしょうか?
今回、仁美役の小野さんも、娘のエリ役の設楽もねさんもオーディションで選びました。
小野さんに関しては、僕がかれこれ10年以上前のことだったのですがCMのお仕事でご一緒したことがあって。今回の仁美役を考えたとき、小野さんのことが思い浮かんで、オーディションがあると声をかけました。
なぜ小野さんの顔が浮かんだかというと、今回の作品はちょっと異色というか。シナリオができた後にまず音楽を作ることにしたんです。だからオーディションの時点で音楽のメインテーマは出来上がっていた。その音楽にマッチするルックの人ということで、小野さんがリンクするのではないかとイメージしました。
それから小野さんは、スチールの世界で長く活躍されている。なぜ活躍できているかというと、顔の表情の作り方が実にうまいんです。能って面をかえて演じ分けていきますけど、そういう感じがあるというか。いろいろな表情を細かく作り分けることができる。だから、静かに物語が進んでいって、さまざまな表情が求められるこの役は合っているのではないかと思いました。
また、日本のホラーですから、貞子しかり、伽椰子しかりで、やはり黒髪で長いストレートヘアがベター。海外へ向けてを考えても、その方がいい。この点も小野さんは合致する。
もうひとつ加えると、映画はやはりサプライズが必要。観客のみなさんは新たな発見を求めている。小野さんはこれまで映画に出ていない。出ることになれば今回が初となる。となれば小野さんが登場するだけで、初というサプライズがある。また、お客さんにフレッシュな驚きを与えられる存在に小野さんがなりうる力があることも僕は感じていました。
実際にオーディションをして、その気持ちは揺るがなくて、むしろ確信をもつに至って小野さんにお願いすることになりました。
――では、設楽さんは?
設楽さんが演じるエリは、母のことを心から愛していて、母親から愛されたい気持ちがすごくある。でも、どこか母の愛情を感じられずにいて、母の愛がほしいがゆえに気持ちが歪んだ方へとエスカレートしていってしまう。つまりあるシーンにおいてはものすごく愛しい存在であることが求められ、ある瞬間においては邪悪な存在になることが求められる。この二つを無理なく共存させられる人を求めていました。
で、オーディションのときに、設楽さんならばできると思いました。それはどこで感じたかというと、いまたとえばエリは17歳の設定ですけど、17歳の女の子を演じてもらうとなったときに、ものすごい苦しみを抱えた子やいまどきのかわいい子、ピュアな心を持った女の子といった役は、けっこうどの若い役者さんも無理なくできるんです。ただ、人をものすごく憎んでいる子はなかなかできない。これはいまの日本の映画にしてもCMにしてもドラマにしても10代の女性は、なによりもかわいいが求められる。だから、かわいくあろうとすることが根付いてしまっている。ダークサイドの感情をあらわにすることなんてほとんどない。ですから、難しいんですよ。ただ、設楽さんはほんとうにオーディションを受けたときがちょうど芸能のお仕事を始めたぐらいのときで。まだかわいいに染まっていなかったからか、憎しみや怒りの感情をストレートに出すことができていた。でも、次には普通の子に戻っている。それで設楽さんにお願いすることにしました。
――では、新たなチャレンジとして取り組んで、その作品が今回の国際コンペティションへ入選しました。このことはどう受け止めましたか?
強豪リーグに入ってしまったなと思いました。
2020年に本映画祭に入選して、ほかの海外作品も拝見しましたが、ほんとうに作品のクオリティが高い。さすが国際コンペティションという作品が顔を揃えていました。だから、また強豪リーグに入ってしまったか、厳しい戦いになるんだなというのが正直な感想です。
ただ、先ほど話しましたけど、映画は海を越えて世界の人々とつながることができる。ですから、この映画は日本の中でも辺境に位置する作品ですけど、ほかの作品と並べてもおかしくない、なにか共鳴するところがあるから選ばれたとそこは自信をもっています。
ホラーということで、どういう反応があるのか気にしながらも、僕自身もいろいろな作品に出会って、映画祭を楽しみたいと思っています。
『マイマザーズアイズ』作品詳細
取材・写真・文:水上賢治