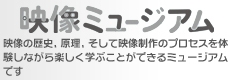【インタビュー】『ブルーを笑えるその日まで』武田かりん監督

――はじめに武田監督は初監督作品の短編『そして私はパンダやシマウマに色を塗るのだ。』が2020年の本映画祭の短編部門にノミネートされています。このときの経験について少しお話を伺えればと思います。
2020年の『そして私はパンダやシマウマに色を塗るのだ。』は、東京工芸大学映像学科映画研究室の卒業制作として大学の仲間とともに完成させた作品でした。もともと卒業制作展の場で上映して終わりだったはずのものが、SKIPシティの映画祭でオンラインでしたけど上映する機会を得て、大学以外の方からいろいろと感想をいただけたのはわたしにとってはものすごく大きな経験になりました。
なによりうれしかったのはわたしを勇気づけてくれる言葉をいくつもいただけたこと。いまも自信はないんですけど、当時はさらに自分が監督をすることに自信が持てないでいました。しかも、卒業制作展でも、担当の教授からもいい評価は得られなかった。
だから、落ち込んでいたんですけど、SKIPシティの上映では好評で、『良いといってくれる人もいるんだ!』と思って、とてもうれしかった。大学よりも温かい意見をいただけて、いい思い出としてわたしの記憶にしっかり刻まれています。
――『そして私はパンダやシマウマに色を塗るのだ。』を発表後、今回の映画『ブルーを笑えるその日まで』にとりかかるまでの経緯を教えてください。
『そして私はパンダやシマウマに色を塗るのだ。』は、卒業制作ということで最後の思い出といいますか。最後にみんなで楽しく作って、楽しく終わろう、みたいな気持ちがどこかにあった。自分の考えていることを全面に出すとか、自分が作りたいものを作るとかよりも、みんなが楽しめるような面白いことをしたい、みんなに楽しんでもらえる作品にしたいという気持ちが第一にありました。それで内容としても自分なりにエンターテインメントに寄せた内容にしたつもりでした。
ところが、教授や知人から『武田さんって普段こういうことを考えている人なんだ』みたいなことを言われたんです。もちろん、わたしが主体となっているので自分の考えが入っているところはあります。事実、途中から自分がこうしたいという思いが出てきて、みんなと喧嘩になって収拾がつかなくなったときがありました。でも、わたしとしては自分のことよりも『みんなに』という思いをもって取り組んだ意識が強い。変な言い方かもしれないですが、よそゆきの恰好をして自分をそこまで出してはいなかった。
だから『武田さんって普段こんなこと考えている人なんだ』と言われたときに、なんだか悲しくなってしまったんです。わたしが普段考えていることとはかなり違う。
ならば、もう自分がいままでずっと思ってきたこととか、誰にも言えないで抱えてきたこととか、自分の思いをありったけ詰め込んだ作品をもうひとつ作ろうと思って。このことが『ブルーを笑えるその日まで』の始まりでした。
――10代のころの不登校や自殺未遂の経験を基にしていると明かされています。無理のない範囲で当時のお話を伺えるでしょうか?
はい。中学生のころだったのですが、クラスにうまくなじむことができなくなり、クラスメイトともうまく話すことができなくなってしまいました。いまこう話していてもちょっと涙が出そうなんですけど、それで学校に行けなくなってしまいました。
そのことをずっと引きずってしまって、高校生のときには自殺未遂を起こしてしまって……。そのときは幸せなことに病院の方や両親のおかげで一命をとりとめました。
この経験は自分の中では今も残る大きな傷。それはコンプレックスでもあって人には言えないこととして、自分の心の中にずっとしまってきました。
でも、あるときニュースを見ていて、日本の10代の死因で一番多いのは自殺ということを知って、ものすごくショックを受けました。もしかしたら、わたしもその一人になっていたかもしれない。なっていた可能性がある。そう考えるととても他人事とは思えませんでした。
年を重ねたいま「あのとき、死ななくてよかったな」と心から思っています。死ななくてもいい道がどこかにあることもわかる。
ただ、当時、大人からよく『生きれてばきっといいことあるよ』と声をかけられて励まされたんですけど、そんな言葉はわたしにまったく響かなかった。そういうきれいごとの言葉をかけてくる大人が嫌いだった。でも、気づけば、わたしも成人していて、もし当時の自分みたいな子に会ったとき、なんて声をかけるだろうと考えたら、『生きていたらなんとかなるから』といってしまいそうな自分がいた。
自分が嫌いだった大人みたいにわたしがなってきつつあるのではないかと思ったらすごく嫌で。
かつてのわたしのように苦しんでいる子に違う言葉をかけたい。でも、うまく言葉で伝えることが難しい。この伝えることが難しい思いを物語にして届けられないかと考えました。
だから、映画を作りたいよりも先に、当時の自分のような子たちに、かつて死にたいと思ったわたしが今も生きていて、なんとかやっていることを伝えることで、「自分も大丈夫」と思ってもらえたら、というものをひとつ形にしたい。まずそういう気持ちがありました。
――その武田さんの切実さが伝わってくる物語だと思います。
ありがとうございます。正直、当時の経験はまだ笑顔で話すことはできません。だから、今でも涙が出そうになる。でも、そう思えるぐらい心の傷としてまだ生々しく残っているうちに、なるべく早く形にしたいと思いました。なぜなら、時間の経過とともにその傷が小さくなるかもしれない。そうなったら、当時の思いを正確に伝えるのは難しくなるだろうと思ったからです。
正確なことを言えば、いまのわたしは当時のような気持ちに完璧にはなれない。
今日だって、雲一つない青空でここに来るまですごく気持ちよくて、幸せな気分で来たんですけど、中学生のころのわたしはこういう晴れた日が大嫌いで、カーテンを全部締め切っていた。
そうなってきているので、当時の思い出せることはできるだけ思い出そうとノートに書きだしていきました。辛かったこと、嫌だったこと、こういう場面ではこんな気持ちになっていたなとか、この一言に傷ついたなとか、あらゆる思いを書き出して、そのノートは6冊ぐらになりました。そうやって書き出したものを基に、ひとつのストーリーを作り上げていきました。
ただ、実体験がもとですけど、実体験をそのまま物語にしようとは思いませんでした。自分のつらかったことや嫌だったことをひたすら映画にするのは表現とは違うなと思って……。辛かった経験をいかに人が見て共有できるものにできるのかを考えました。ひとつのエンターテインメントとして成立させたいと思いました。

©ブルーを笑えるその日まで
――物語は、学校で飼育されていた金魚の死に、それまでめんどうをみることがなかった生徒たちが口々に「かわいそう」という。それに対し主人公のアンが心の中で明かす「この世界では、死なないと優しくしてもらえない」というドキッとした言葉から始まります。
若い子たちの自殺の根本には、「この世界では、死なないと優しくしてもらえない」があるのではないかと思いました。
たとえば中学生の自殺がニュースで報じられると、知人や近所の人のインタビューで「いい子だったのに」とか「最近ちょっと元気がなくて気になっていた」とか言って悲しむ。「なんで死ぬ前にもっと気にかけてやさしくして接してくれなかったのか」と思ってしまう自分がいます。亡くなってから悲しんだり優しくしたりしても遅い、とやるせない気持ちになってしまう。
わたしの体験を話すと、中学校で学校へ行けなくなったときに、クラスのみんなから謝罪のお手紙が届いたんです。わたしを無視したり、わたしにいじわるをしたりといった女の子たち全員からたくさん。不登校になった夏休み明けからしばらくしたころに。で、このころというのがちょうどわたしの誕生日だったということで、たくさんのプレゼントと一緒に。
わたしにとって、このときがいまだに人生で一番プレゼントをもらった日なんですけど、まったく喜べなかったし、なんだか釈然としなかった。むしろ昨日までいじめてきた人が急に謝罪してくることが怖かったし、その後、トラウマになって誕生日が苦手になりました。
そういった思いを、「この世界では、死なないと優しくしてもらえない」という言葉に込めて物語の始まりにしました。
――主人公のアンは中学生で友人たちには無視され、人の前でうまく話せない。クラスで孤立していつもひとりぼっちでいる彼女は、ある日、不思議な商店のおばちゃんからもらった万華鏡を手にする。覗いてみると立入禁止の屋上の扉が開き、そこでアイナという生徒と出会う。同じような悩みを抱えて急接近した二人が前を向いていく物語になっています。
中学生のころの自分のように苦しんでいる子たちの心に届くものにしたいと思いました。ただ一方で、当時のわたしがみて嘘、きれいごとを並べているような作品には絶対にしたくなかった。
自分を肯定できるような物語にはしたい。でも、安易な希望を見せるものにはしたくない。どうすればそういう物語にできるのかが一番の悩みでした。
アイナがアンにどういう言葉をかけるかなど、ほんとうに悩みっぱなしで何度も改稿を重ねました。
あれこれとセリフを書いていたんですけど、むしろそういった言葉よりも、アンにとってはアイナが一緒にいてくれること、見守っていてくれること、味方でいてくれることが重要ではないかと思って。言葉よりも態度というか。いまのような言葉だけじゃない心の
コミュニケーションで二人が分かり合うような形の物語になりました。
ただ、いまだにもっといい表現方法があったのではないかと考えてしまいます。
――ひじょうに武田監督の思いがこもった、当事者の心の声が聴こえてくるような物語になっていると思います。
いろいろと伝わってくれたらと思うことはあるのですが、中でも、なんとかなるといいますか。
ちょっとわかりづらくなってしまったんですけど、金魚のお墓の花が枯れてしまっているシーンがあるんです。
はじめはみんながかわいそうといってお墓を作って手を合わせた。しばらくは花が供えられる。でも、少しするともう誰も気にしなくなって花を供えることもなければ見向きもしない。そして最後に供えられた花が枯れて朽ちていく。つまり死んでもこのようにあっという間に忘れられて、そんなことがあったかぐらいになってしまう。
いじめにあって苦しくて苦しくて死を選んでしまっても、それぐらいのことで済まされてしまう。だから、苦しいかもしれないけど、死を選ばないでほしい。そういう思いをこのシーンでは伝えたかった。
この物語を通して、いろいろと伝わってほしいことはあるのですが、命を捨てないでほしい、大事にしてほしい。そのことが伝わってくれたらと思っています。
――そのような伝わる物語にするには、アンとアンナを体現してくれる役者さんの存在が不可欠だったと思います。アン役の渡邉心結さん、アイナ役の角心菜さん、ともにすばらしかったと思います。
お二人ともオーディションだったんですけど、渡邉さんも角さんも会った瞬間に、アンとアイナはこの二人と一瞬で決まりました。
まず、渡邉さんのお話しからすると、アンという人物を語る上で、彼女の存在は欠かせません。渡邉さんがいなかったら、アンはできていなかったかもしれない。それぐらいアン役を作り上げていく上では、渡邉さんの存在が大きな力になってくれました。渡邉さんといろいろと話し合った中でアンがひとりの人間になっていったところがあります。
アンは一言で表すなら、暗い性格ですけど、実際の渡邉さんはめちゃくちゃ明るい。いまどきの言葉で言えば、陽キャなんです。
じゃあなんで渡邉さんを選んだかというと、むしろアンと真逆の性格をした子に演じてほしかった。真逆の子と作りたい気持ちが自分にはありました。アンともわたしとも違う性格の子と組んでみたかったんです。
なぜかというと、逆の性格だからこそ話し合ったら何か新しい発見があるのではないかと考えました。わたしと似たような性格の人と組んでも『そうだよね、わかるわかる』みたいな感じで終わってしまうのではないかと思ったんです。
わたしは不登校でしたけど、学校に楽しく通っている子にとって見えていた風景はまったく違うはず。その視点もいれたらもっと作品の世界が広がるのではないかと思いました。
すごくよく覚えているのが、オーディションのときに渡邉さんが同じクラスに不登校の子がいたことを話してくれたんです。そのとき、渡邉さんは「なんで来れないんだろう」と思っていたとか、いろいろと話してくれました。
わたしはまさに不登校のサイドだったから、学校で楽しく過ごしている人のことがわからない。渡邉さんから話をきいて、はじめて不登校の子を普通に学校に通っている子たちがどうみているのか、ちょっとわかったんですね。それで、渡邉さんの視点でみたアンを入れることでなにかが生まれるのではないかと思いました。また、自分とはまったく違う学校生活を送っているアンを通して、渡邉さん自身もいろいろと考えて、そこからも何か出てくるのではないかと思いました。
だから、渡邉さん抜きにしてアンは成立しなかったと思います。その気持ちは撮影中も、撮影を終えた今も変わっていないです。ほんとうに大きな存在だったんです。
撮影当時、渡邉さんは中学三年生で、わたしが初めてお会いしたオーディションのときはアンと同じ中学二年生でした。わたしと彼女は年齢で10歳ぐらい違う、年下の女の子なんですけど。アンを演じてもらう上で、わたしのことを知ってほしくてけっこういろいろと自分の中学時代のことを赤裸々に話したんです。撮影前も撮影中も。いま考えるとヘビーな話ばかりをしてしまったなと反省するしかない(苦笑)。しかも、さきほどお話したように、中学時代のことを話すとどうしても涙が出てきてしまう。10歳年下の子の前で恥ずかしいんですけど、泣きながら話す。そんなわたしを彼女は何度も抱きしめてくれました。どっちが年上かわからないですよね(笑)。ほんとうに彼女には助けてもらいました。すばらしい女優さんです。
――アイナ役の角さんは?
物語上、あまり詳細は明かせないんですけど、存在がファンタジーみたいな。現実感があるようでないようなそういう感じの人がいればなと思っていて。そこに現れてくれたのが角さんでした。
物語を、アンを、いろいろな意味でリードしていく存在で、作品においてかなり大きな役割が課されている役なんですけど、見事に演じ切ってくれたと思います。
それから、角さんもわたしの気持ちを受けとめてくれた一人。涙を流すシーンがあったんですけど、ちょっとうまくいかないでいた。それで少し時間をとって、わたしがまた涙目で自分の話をしたら、その話を角さんは全身ですべてを受けとめてくれて一緒に泣いてくれたんです。「ここだ」と思って、そのまま撮影をスタートさせました。
渡邉さんといい、角さんといい、わたしはまだ若い二人にかなり助けられました。
――劇中で、RCサクセションの「君が僕を知ってる」が使われています。これも物語にリンクしていいですね。
まさか使用させていただけるとは!といった気持ちです。
この曲はわたしがもともと大好きで中学生のころによく聴いていました。わたしにはそういう存在がいなかったんですけど、だからこそ憧れていて、自分にもそんな存在がいてくれたらなと思っていました。
それで、今回の脚本を書き始めるときに、この曲の二人のような関係を描きたいと思いました。アンにはアイナがいて、アイナにはアンがいる、そうやって二人でいれば生きていける。そこからぶれないようにと思って脚本を書き進めました。
いつも脚本を書き始める前に、まずこの曲を聴いて気合いを入れてから、書き始めました。脚本を書いている間もずっと聴いていました。
そのことをプロデューサーに話したら、主題歌にできないかという話になり……。恐れ多い感じで事務所にお手紙を書いたんですけど、承諾をいただくことができました。
――自身の思いの詰まった作品が今回、入選しました。その報せが入ったときはどんな気持ちでしたか?
速攻でスタッフの人たちに報告しました。「入選しました」というと、みんな大喜びしてくれました。
多く人の協力があって完成した作品でしたから、このような大きな映画祭でお披露目の機会をいただけて、少し肩の荷が下りてほっとしました。
――今回の映画祭はどんな場にしたいですか?
そうですね。前回はオンラインで直接感想をいただくことができなかった。でも、今回はスクリーンでの上映もあるので、やっぱり観客のみなさんの生の感想をきけることが楽しみでもあり、ちょっと怖くもあります。
あと、なかなか難しいかもしれないですけど、10代のわたしのような子が会場に来てくれて作品を見てくれたらうれしい。そういう子たちから感想をいただけたら、うれしいですね。

©ブルーを笑えるその日まで
――では、ここからはプロフィールの部分を聞いていきたいのですが、映画に興味をもつきっかけは?
こんなことを話すと『映画への愛がない』と怒られそうなんですけど(苦笑)、ずいぶん遅くて。お話ししたように中学時代は不登校で、高校時代も友達があまり作れない、人とうまく話せないでいました。その中で、人と関われないけど、人と関わりたいと思って、絵をずっと描いていたんです。
美術の先生に課題を出していただいていたんですけど、あるとき、映画の名作をみて、好きなワンシーンで止めて、それをクロッキー(素描)して、構図の勉強をしなさいと言われたんです。
そこで見たのがスタンリー・キューブリック監督の『時計じかけのオレンジ』で衝撃を受けました。最後のクレジットをみていたら、いっぱい人の名前が出てくる。「映画ってこんなに多くの人たちが関わっているんだ」と思いました。
この映画原体験があったとき、ちょうど進路を決めないといけない時期に差し掛かっていました。このまま絵の勉強を続けようと思ってアート系の学校に進もうかなとも思ったんですけど……。漠然とですけど将来を考えたとき、この先もひとりでずっと絵を描き続けているのは嫌だなと……。きちんと人と関わってモノづくりをしてみたいと思いました。
そのとき、映画のエンドクレジットのことを思い出して、あの中の、ほんとうに片隅でいいので一人にだったらなれるかもしれない。あの大勢の中の一人にならば自分でもなれるかもしれないと思って、映画の学校に進むことを決めました。
――それで、東京工芸大学映像学科映画研究室の方に進まれる。
そうです。とにかく映画のクレジットの中のどれかになれればよかったので、主に自主映画でしたけど、大学の先輩の作品の制作部をやったり、助監督をやったりと、いろいろな現場を経験していました。
ただ、監督は一度もしたことがありませんでした。
――それが卒業制作として『そして私はパンダやシマウマに色を塗るのだ。』を作ることになった?
実ははじめ自分が監督をすることは考えていませんでした。ただいろいろあって卒業制作展で、監督をやるという生徒がなかなか現れなくて、回りに回ってわたしがやることになったんです。
人とコミュニケーションをとるのがいまだに下手なので、まさか自分が監督をやるとは思っていなかったし、向いているともできるとも考えていなかった。
だから、いまだに自分が監督をやっているのが不思議で。向いてないのに大丈夫かなと思って続けています。
あと、余談になるんですけど、もともと好きだった絵は大学に入ってやめてしまったんですけど、大学卒業した春にコロナ禍になって、なにもできない状態になって、再び描くようになりました。いまちょっとイラストの仕事もしていて、絵を描いていたのも無駄じゃなかったんだと思っています。
――今後も映画監督を続けていきたい?
向いていないと思うんですけど(苦笑)、続けていけたらと。
今回、自身の体験を基にしたので、もし次が叶うなら、今度は自分の体験しなかった人生を、物語を通して経験してみたい気持ちがあります。
『ブルーを笑えるその日まで』作品詳細
取材・写真・文:水上賢治