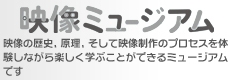【インタビュー】『繕い合う・こと』長屋和彰監督

――長屋監督はこれまで役者として映画やドラマ、舞台などに出演してきました。今回、初めて監督に挑むことになったわけですが、そういう意欲が依然からあったのでしょうか?
いや自分が監督をやることはまったく考えていませんでした。
――では、なぜ(笑)?
監督をすることは考えていなかったんですけど、2015年ぐらいから脚本を書き始めるようになりました。役者を続けていく上で脚本への理解をもっと深め、脚本をもっと読み解く力もつけたくて脚本の講座に通って勉強していたんです。それで時間があるときに、あくまで趣味という形で、自分で(脚本を)書くようになりました。
ただ、あくまで役者の仕事にプラスになればというだけであって、監督して映画にしようと思うことはなかった。というかそもそも脚本を書き始めてはみるんですけど、最後まで書き終えることがなかったんです(苦笑)。
実際に書いてみると、自由に書いている分には楽しいんですけど、次第に、こんなシーンあったら、どうやって撮るんだよとか、こんなシーン撮ろうとしたらお金かかりすぎてダメだろうとか、余計な視点が入ってきてしまう。映画を作るのって頭を悩ませることばかりだなと思うと、筆がだんだん進まなくなって、役者だけやっている方が楽だなとか思って、書き終えるまでいかない。
その中で、唯一、最後まで初稿で叩き台ぐらいでしたけど、自分の中でひとつのストーリーを最後まで書き終えたなと思えたのが実は今回の『繕い合う・こと』の脚本でした。
初めて最後まで書き終えた脚本でしたから、やはり誰かに読んでもらいたい。そこで知り合いの監督さんにお願いして読んでいただいたんです。すると、その監督さんに『最後まで形にした方がいいよ』と言われて。つまり映像にして形にした方がいいとアドバイスを受けました。そのとき、「じゃあ、ちょっと頑張ってやってみようかな」と心が動いたのが今回の作品のスタートでした。
――自分で監督をしてみようと心が動いた理由は?
これまで役者をやってきて、『カメラを止めるな!』に出演することができた。出演後、ありがたいことに、いただけるお仕事が増えました。ただ、どうしても役者って受け身のところがある。役をいただいてから始まる、役をいただけなければ何も始まらない、みたいな感じがすごくもどかしくなってきていました。
自分から発信していく、主体的になにかをやる、そういう風に動ける機会はないかなと考えていました。ただ、その時点でも監督をしたいとは思っていませんでした。
そういった思いがある中で、今回の脚本を書き上げたとき、この脚本をお願いしますと、誰かに渡すのはすごく嫌だなと思ったんです。初めて形になったものだったので、なんか他人に渡すことにためらいを覚えた。そのとき、はじめて「じゃあ自分で映画にしてみようかな」となりました。あとで、それがどれだけ大変なことなのかわかって、顔が青ざめるんですけど(苦笑)。
――この脚本に関しては、最後まで書くことができた理由はなにかありましたか?
本作の場合、脚本を書く時に物語のおおよその全体像よりもシーンが先にあるというか。こういうシーンがおもしろいんじゃないかとか、こういうシーンがあったらなとか、わりとまずシーンが先にあって、そのシーンをまずはパーツパーツで書いて言って、このシーンとこのシーンをつなげるには何が必要で、どうすればいいか、といった形で一つのストーリーになるみたいな感じで脚本を書いていました。
当然ですけど、パーツパーツでつながらないこととかでてきて、どうにもならないといった感じになることが多々あったんです。でも、『繕い合う・こと』の脚本については、ぴったりはまっていって書き終えることができました。
あと、こう説明すると順風満帆に書き上げたように映るんですけど、そんなことはなくて(苦笑)。途中で行き詰ったんです。漠然と兄の方が日本の伝統的な仕事をしている気持ちがあったんですけど、なかなかどの仕事にすればいいか見つけられないでいた。そんな折、脚本の相談をした監督さんに誘われてある映画祭に行ったとき、1本のドキュメンタリー映画を見たんです。それが海外の監督が撮った「金継ぎ」についてのドキュメンタリーで、ものすごく興味をもったんです。
その作品に金継ぎの職人の方が出演していらっしゃったんですけど、調べてみたら、ワークショップをちょうどやられていた。それで講座を受けてみて、お話もちょっと伺うことができたんです。
金継ぎが象徴している、「一度こわれたものを再びつなぐ」ということが、なんかいいなと思って、作品の根底に流れるテーマにもなってくれるかもしれないと思いました。それでピースがはまって一気にといった感じだったので、金継ぎとの出会いも大きかったです。
いま金継ぎはちょっとブームみたいになっていて、テレビでもたまに見かけますけど、当時、僕はまったく知りませんでした。映画祭に行かなかったら、おそらく出会っていなかったと思います。そういう意味で、運命的な出会いだったといっていいかもしれません。

©2023 Kazuaki Nagaya
――作品は、亡き父の跡を継いで、金継ぎ師になった兄の護と、自由気ままに生きる弟の幹の物語。お互いにちょっとしたわだかまりを抱えている二人の関係が、繰り返される日常と、その中にある小さな変化とともに描かれます。
数あるドラマや映画の中には、極端に仲のいい、もしくは仲の悪い兄弟が描かれる作品も見受けられますが、護と幹はどちらでもない。お互い視野には入っていて気にしていないことはない。でも、密にコミュニケーションをとるわけではない。微妙に距離があるけれど、遠い存在ではない。そんな感じで、個人的にはリアルな兄弟像だと思いました。
僕は二人兄弟なんですけど、いまおっしゃっていただいたような感じで、そんなに話をするわけではないけれども、別に仲が悪いわけではない。久々に会ったからといって近況をお互い報告するわけではない。そういう兄弟の在り方が普通だったんです。ギクシャクしているわけではないけれども、はたから見ると距離があるようにみえる。そんな兄弟関係を描きたいと思いました。
それはなぜかというと、なにか特別な兄弟の関係よりも、いわばありふれたごく普通の当たり前のような兄弟関係を描きたい気持ちがありました。僕にとってリアルな兄弟像は、護と幹のような感じで。平凡かもしれないですけど、つかず離れずのこんな兄弟を映画で描いてもいいのではないかと思いました。
それは物語全体でも考えたことで、日常の暮らしや日常の風景を丁寧に描こうと思いました。護がいつもきちんと食事を作って食べるというのもそういう考えから、丁寧に映し出していこうと思いました。
付け加えると、僕がこの兄弟で描きたいのはこんな感じですということで、スタッフやキャストには石井裕也監督の『ぼくたちの家族』を見ておいてくださいと伝えました。
――セリフを極力絞って、ほんとうに目の前で起きていることを見せてストーリーを進めていくような演出になっている印象を受けます。
一番はリアルを目指したところがあって、説明的なものは省こうと思いました。だから、当初に比べると、自分でも「説明がなさ過ぎてわからないのではないか」と思うぐらい、セリフもかなりばしばし切ってしまったんです。最近、予定していたシナリオを見たんですけど、いまとぜんぜん違うものになっていました(苦笑)。
ただ、自分としては、きちんとみなさんが余白を読み解いてくれて想像してくれる作品になったのではないかなと思っています。
――ここからはキャストについて話をききたいのですが、主人公の兄・護はご自身で演じられています。これは当初からそうしていたんですか?
いや、当初は、自分は小さな役で出られればいいぐらいに思っていたんですけど……。実際、護役を演じてもらうとなると、まず金継ぎを最低限のところまではマスターしてもらわないといけない。そうなると、金継ぎの講座を受けていただいたりとかなり時間を費やしていただかなくてはならない。
その手間暇を考えると、もう自分しかいないというか。一応、その時点で僕は金継ぎも学んでいたので、ある程度はできる。で、自主映画ですから予算が潤沢にあるわけではない。僕が主演を務めれば、予算も抑えられる(苦笑)。自分で脚本も書いているので、キャラクターについてもすでにつかんでいる。
そういったもろもろを合わせるとというか、かなり必要に応じてですけど、もう自分がやるしかないのかなということで、護役は自分が演じることになりました。
――監督をして、主演も務めるのは大変だったのでは?
大変でした。監督を務めるのならば、主演はしないということを学びました(笑)。監督・主演をやられている方が多くいらっしゃいますけど、僕はちょっと無理です。両方やると、もういっぱいいっぱいで頭が回らないです。
――一番、きつかったのは?
撮影後の編集です。自分の演技が見ていられなくて、どれだけカットできるかしか考えていなかった。でも、主人公だから出さないわけにはいかないしで、きつかったです。
現場のときはあまり感じなかったんですよ。自分が演じるときはスタートだけスタッフに言ってもらって、カットは自分でかける。それで撮ったものをモニターで現場でちゃんと確認して、大丈夫だと思ったらOKで、ダメだったらもうワンテイクとなる。
比較的冷静に判断してやっていたんです。やれていたと思っていたんです。ところが編集で見てみると、なんか違う。「この芝居はなんなんだ」と。こそばゆいというか、居心地が悪いというか。そのことも含めて自分が監督をするときは主演はやめとこうと思いました。
――その護の弟の幹役は、黒住尚生さんが演じられています。いまいろいろな作品への出演が続いています。
彼とは、『カメラを止めるな!』のときのワークショップで出会いました。最終的に僕は『カメラを止めるな!』の方に出演することになって、彼は別の監督の作品の方に選ばれたんですけど、ワークショップの間、比較的年齢が近いこともあって親しくなりました。それでワークショップ後もときどき会うような仲になっていました。
僕はワークショップのときから、彼の芝居がすごく好きで。いつか一緒に芝居ができたらなとずっと思っていたんです。ただ、待っていても共演するチャンスはなかなかないだろうと思ったんですよね。まあ普通に確率として考えても、キャラと年齢の近さから一緒にキャスティングされる可能性は低いかなと。で、この企画をやろうとなったとき、真っ先に思いました。「彼を誘おう」と。
あと、脚本を書いていた段階から、黒住くんと一緒にやってみたい気持ちがあったので、彼を想定して兄と弟の話でと漠然とですけど考えていたところもありました。
――実際に組まれてみて、どうでしたか?
いや、僕が言うのも変ですけど、いい役者だなと思いました。僕は彼の意見や視点にものすごく信頼を置いているところがあるんです。たとえば今回の脚本も、忖度なしにずばずばと自身の意見を言ってくれる。彼の意見やアイデアを取り入れているシーンがけっこうあります。
――では、初監督を終えてのいまの気持ちは?
いままで役者として数多くの作品に携わらせていただいて、さまざまな監督とご一緒させていただきました。そのすべての監督たちがどれだけすごいのかを痛感しましたね。みなさんに改めて尊敬の念を抱きました。
わかっていたつもりでしたけど、監督の仕事はやらなくてはいけないことだらけ。俳優が知らないところで動き回っていることを実感しました。たとえば、演出一つとっても、相手にどういう言い方をすれば伝わるのか、どういうコミュニケーションを図っていけばいいのか、などとことん考えないといけない。自分のビジョンがあるのであれば、それを言葉できちんと説明をし尽くさなければならない。いままで自分は演出を受ける立場でしたけど、する側に立って、こんなにも難しいものなのかと感じました。またいままでもきちんとしてきたつもりですけど、役者として立ったとき、いただいた演出の言葉はしっかりと受け止めないといけないなと思いました。
あと、個人的な話になるんですけど、直接物語に反映させることはしていないのですが、今回の作品を作るひとつの原動力として、一人の友人の存在がありました。学生のときに亡くなった友人です。
彼とはものすごく親しいというわけではありませんでした。高校一年生のときに一緒のクラスで仲良くなったのだけれど、2年生でクラスがかわってからは、廊下で会えば話をするぐらいの間柄でした。ただ、いつも気にとめている存在ではありました。でも、高校三年の卒業間近に亡くなってしまった。このことが僕の心の中にはずっと残っていました。
それで、なんかことあるごとに、もっと生きたかったはずの彼より、自分は長く生きているのに胸を張れた生き方ができているのかなと思うんです。また、そういうときにしか彼のことを思い出さないこともすごく嫌だった。
で、彼に対して何か胸を張れることをしたかった。本作で答えを出せたかはわからないですけど、それでも彼に伝えられるものがひとつできたかなと思っています。
――苦労して完成した作品が入選しました。今の気持ちは?
まず一番に、やっといろいろな方に見てもらえる場所に出せるということで安心しました。作品を作るに当たってはほんとうに多くの方に応援していただいて、多くの支援をいただきました。でも、ずっとお披露目できてこなかったので、やっと見てもらえる機会に立てたことで安心しました。
映画館での劇場公開を目指しているので、今回の映画祭が名刺代わりになって、次につながっていってくれたらと思っています。そのためにも今回の映画祭でひとりでも多くの方に見ていただいて、いい形で終われたらと思っています。
――監督は今後も続けていきたいですか?
そうですね。不器用な性格なので難しいかもしれないですけど、またいい機会がめぐってきたらやるだろうなと思っています。
ただ、あくまで本分は役者です。あくまで役者としてやっていくことを大切に第一に考えてやっていって、その上で(監督の)チャンスがめぐってきたらというスタンスでやれたらなと思っています。
『繕い合う・こと』作品詳細
取材・写真・文:水上賢治