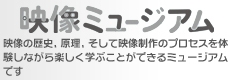【インタビュー】『十年とちょっと+1日』中田森也監督

――はじめに、ほんの数年前、2020年ぐらいから自主映画制作を始めたとのこと。映画作りを始めたきっかけを教えていただけるでしょうか?
こういうと怒られそうなんですけど(苦笑)、もともとシネフィルで映画をめちゃくちゃ撮りたいと思っていたわけではなくて。大学で映画を学んだり、映像系の専門学校に行ったりしたこともないんです。だから、自分が映画を作れるとは思っていなかった。
ただ、少し前から技術の進歩がすごくてカメラが手に入りやすくなって、そのうちスマホで映画が撮れるといった情報が、僕にですら入ってくる。そういった情報に触れたときに、いままでまったく考えたことはなかったんですけど、ふと「誰かと一緒に創作活動を一度してみたいな」という気持ちが芽生えたんです。わからないですけど、人と何かを作ってみるって面白いかもしれないと、思ってしまった。もしかしたら自分も映画が作れるかもしれないぞと思ってしまった。それがきっかけです。
――おそらくはじめは右も左もわからない状態だったと思うのですが、それからどうやって自主映画制作を始めていったのですか?
まず人と一緒に映画を作ってみたい気持ちがあったので、まずは人脈を作りたいなと思いました。いろいろと探してみると、みんなで自主映画を撮ろうみたい集まりがありました。まず、それにスタッフや役者と出会えればなと思って参加しました。そういった感じで自主映画の世界に入っていった感じです。
――そうやって人脈を作って2020年ぐらいから自主映画制作に乗り出した?
そうですね。2018年か2019年ぐらいだったと思うんですけど、自主映画の監督とお話する機会があって。その監督から「年をとると自主映画はどんどん撮りづらくなるぞ」といったことを言われたんですね。そのころ、僕は30歳をちょっと超えたぐらいで、年齢的にいま動かないとタイミングを逃すか、もう少し後だともう完全にアウトになるかもしれないと思って、とりあえず自分でも作ってみようと動き始めました。

©中田森也
――では今回の映画『十年とちょっと+(たす)1日』のお話に入りたいのですが、どういった発想のもと、脚本は作っていったのでしょうか?
お恥ずかしい話ですが、コロナ禍になって1年ぐらい経ったとき、仕事がなくて1日中ゲームをしていた時期があったんですよ。二カ月ぐらいですけど、朝から晩までゲーム三昧みたいな。で、さすがにこのままではまずい、そろそろ働かないとと思って(笑)。同時に、脚本も書いてみようかとなった。そんなことがあって、今回の作品に少し残ってますけど、まず「一日中ゲームをしている人」というところが出発点といえば出発点になって脚本を書き始めました。
そこから始まって、こういう物語にしようとか、こんな全体像でみたいなことは一切考えないで、会話のやりとりをひたすら書いていきました。その中に、これまで自分が生きてきた中で経験したこととか、聞いたこととか、心に引っかかったこととか、実際に見た風景だったりとか、そういったものを反映していって、人物のキャラクターやシーン、物語の舞台などひとつひとつを作っていった感じでした。
ですから、明確に元となった出来事があったり、人物がいたり、というわけではありません。監督メッセージでも少し触れたんですけど、過去に見たり、経験したりといった様々なことを思いながら、脚本の執筆を始めて。かつて自分の経験した世界が形を変えて、言葉になって、人物になっていってひとつの物語ができたような感覚でした。
――作品は、地元を離れ都会で暮らす原崎、菊島、森田の男女3人がたまたま地元に戻ってきていて10年ぶりに再会します。菊島と原崎は過去にひと悶着あったけれども、3人とも特に仲が良かったわけでも悪かったわけでもない。なので、少し距離がある。そこに菊島の婚約者の男、時岡も加わって、彼らの言葉の応酬が始まります。この会話が秀逸で、世間話とはいわないけれども、ありふれた日常の会話をしていたと思ったら、ある瞬間から互いに差し違えるかのような緊迫感ある対話が始まる。その交わされる会話は意味があるようにも、ないようにも映る。その言葉のやりとりから目が離せなくなります。
たとえば、言葉を厳選してセリフを練りこんで練りこんでといったような意識は書いている上ではありませんでした。ただ、今回の作品の前に何本か自主映画を作ったんですけど、セリフのやりとりが納得いくものにならなかった。
役者さんには当然、言いやすい言葉や言いづらい言葉があって、言いにくい言い方や言いやすい言い方もある。ただ、役者さんが言いやすい言葉で言ってもらうと、映画としておもしろくなくなってしまったり、なんかちょっと違和感があったり、ということになることがある。
そのバランスが難しくて、僕の課題だなと思っていました。だから、今回に関しては役者さんがやりやすい+きちんと映画として成立する、映画的な会話や対話、言葉になるようにずっと考えていたところはありました。セリフについては書いたら、何度も何度も自分で口に出して言ってみるんですけど、その言葉の推敲をとことんやって、突き詰めました。
あと、ある種の会話劇になったのは苦肉の策といいますか。そもそも自主映画で低予算ですから、たとえば派手なアクションとか、ものすごいロケ地を使っての撮影とか、できないわけです。そういう中で、なにかおもしろいことができないかと考えると、人と人のやりとりとか、魅力的な人物を作るとかしかない。それで僕の場合は前回の反省もあって、言葉に力を入れてみた。それでこのような形になったところがあります。
――役者さんも演じるのがそうとう大変だったと思うのですが、どのような話し合いをされたのでしょう。
おそらく通常ですと、脚本を読み込んでもらって、自分の演じる人物の理解を深めて、リハーサル、本番に挑む、といった流れだと思うんですけど、今回の場合は、どんな人物なのかを想像するのをやめてもらったというか。言葉を交わす中で、ぴったりくる、しっくりはまる動きだったり、言葉だったり、言い回しだったりを探してもらいました。まずは相手の声に耳を傾けて、それを受けて言葉を返すみたいなことをやってもらいました。役というよりは自分自身という人間の延長線上で探ってもらって、それをそのまま出してほしいということを伝えました。
――なぜ、そうしようと?
たとえば役者さんが役になりきった演技や練りに練って作りこんだ芝居を否定するつもりは毛頭ないんですけど、僕は俳優さん自身のなにかが出ているような芝居の方がしっくりくるというか。端的に言うと、その方が好きなんです。
過去の経験から言うと、たとえば役者さんてカットと言って終わったあとの方が、自然な魅力あふれる表情になっている。演じていないときの方が、実にいい話し方で生き生きしているときがある。そういうところを自分は引き出して、できれば収めたい。その人の持っているものの延長線上にあるものをみたい。ということで、こういう試みをしてみました。
こうかっこいいこと言ってますけど、すべてはスタッフのおかげだと思います。僕は撮影時、ヘルニアでほとんど使い物にならないような状態でしたから、優秀なスタッフと役者さんのおかげでいい形になったと思います。
――言葉のやりとりがすばらしくて、どうしてもそちらを注視してしまうのですが、見終えたときに、なんともいえないノスタルジックな気持ちになるところがありました。ここに登場する人物を見ていると、「あのころ」の自分を思い出すような気分になります。
その質問に対しての正確な答えになるかわからないんですけど、自分の記憶の中に忘れられない記憶みたいなものがあって、それをどうにかして残せないかなという思いがありました。そして、それが見てくれた方の記憶に残るものにならないかなということを一番に考えて作りました。
久々の再会を果たす同級生の三人は、地元から外へと出たこと、現在、自分の生き方をみつけられないでいる点が共通している。それぞれ訳あって地元に戻ってきたのだけれど、すでに地元に居場所はない。そのことから開き直って気楽に生きられる性格でもない。なにか中途半端で、先が見えない。
振り返ると大したことはないと気づくんですけど、そのときは途方に暮れ、自分の立っている場所がわからない。そういうもどかしい時期が誰にでもあると思うんですよね。そんな、あのころの切実さを、掬い取って、伝わってくれればうれしいです。

©中田森也
――物語を描く上で、なにか参考にした映画や創作物はありましたか?
ないですね。ただ、元ネタがあるわけではないんですけど、漫画原作を自分で映画化したらという気持ちで取り組んだところはありました。
スタッフの何人かが漫画好きで、彼らに脚本について「漫画ですね」といわれたので、自然と出ているんだと思います。漫画がもっている世界観や、漫画ならではの手触りみたいなのものがあるじゃないですか。それが好きで、なんか漫画がもっているテイストを、映画でも出せないかなと考えています。
僕は感性が鋭くないので、無理だろうなとは思うんですけどね(苦笑)。漫画がもっている感触や感覚を、いつか映画で同じように表現できないか考えています。
――自身の創作をする上で、影響を受けている作品はありますか?
宮崎駿監督のアニメーション映画『ルパン三世 カリオストロの城』は影響を受けていると思います。実写ではないですけど、映画としてあの作品のもつ力に憧れています。
――今回、入選の報せを受けたときはどんな感想を?
驚きました。素直にうれしかったです。作品を作り終えたときは、先ほども少しお話ししたように、役者とスタッフに助けられっぱなしで、自分の至らなさを痛感していました。ですので、これでひとつ恩を返せたかなと思いました。
初めての映画祭でどうなるのかわからないですけど、とにかくみていただけるだけでうれしいです。
『十年とちょっと+1日』作品詳細
取材・写真・文:水上賢治