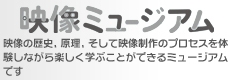【インタビュー】『ヒエロファニー』マキタカズオミ監督

――マキタ監督は過去に発表された短編『アイノユクエ』『これからのこと』『産むということ』の3本がいずれも本映画祭に入選。SKIPシティ国際Dシネマ映画祭を知る人にとっては、待望の長編だと思います。3本の短編を経て、「次は長編」という気持ちはありましたか?
これまで短編を作ってきて、長編が視野に入っていたのは確かです。
知り合いの長編映画が劇場で公開されたり、僕自身も長編の脚本をいくつか書かせていただいたりして意識するようになっていました。「(長編を)脚本だけではなくて、自分で監督して撮ってみたいな」と。
ただ、短編を経て、「次はそろそろ長編を」という気持ちはなかったです。短編は短編で大好きなのでこれからも作っていきたいと思っているので。
だから、「次はそろそろ」といった気持ちはなかったんですけど、一度、どんなものなのか長編を作ってみたい気持ちはありました。
――なるほど。そういったお気持ちがある中で、今回の長編『ヒエロファニー』はどういう形でスタートしたのでしょう?
僕は「elePHANTMoon」という演劇ユニットを主宰しているんですけど、就職やいろいろなことが重なって8年ぐらい活動をしていなかった。そんな折、ある演劇祭から、「elePHANTMoon」で出ませんかと打診があったんです。
じゃあ、せっかくだからということで仲間に声をかけて久しぶりに本公演をやろうかとなったんです。はじめは演劇公演を考えていた。
ところがコロナ禍になってしまって、舞台をやるのはリスクが高くてちょっと難しい。でも、仲間に声をかけて集まってくれたので、なにかやりたい。感染防止対策をしっかりとやれば、映像ならなんとかできるかも。ということでじゃあ長編を撮ってみようと思ったのが出発点です。
――では、脚本は同じものを?
舞台とは別のものを書くことにしました。
まず何を作ろうかとを考えたんですけど、もともとホラー映画が大好きだったのに、これまであまり作る機会がなかった。ただ、ここ数年の間に、ディレクターとして「ほんとにあった!呪いのビデオ」や心霊ドキュメンタリー番組に携わりました。で、改めて好きと言っているわりには、これまでホラー映画は撮ってこなかったなと思って。初心に帰るじゃないですけど、ならばホラー映画を作ってみようと思いました。
――目指したホラー映画はあったのですか?
そうですね、海外ホラーに多いですけど、ゴーストだったらゴーストがはっきりと画面に登場してくるタイプの作品が僕は好きなので。日本のぼんやり映っていてだんだんはっきりと見えてくるといった感じではない、そのものがずばり最初からはっきりと出てくるホラー映画を作りたいと思いました。
――作品は、宗教色が強く入ってくる内容ですが、なにかベースに置いたものはあったのでしょうか?
僕自身は信者ではないのですが、昔から聖書が好きでよく読むんです。ご存知でしょうけど、海外のホラー映画は、けっこうキリスト教をモチーフにしていることがある。そこで、自分も聖書からなにかひとつ物語を作ってみようと思いました。
同時に当時、ある仕事の撮影で今回の舞台になっている大磯教会をたまたまみたんですけど、「ここで何か撮りたい」と思ったんですよね。もうこれは直感でしかないんですけど、この教会で何か撮りたいという衝動にかられた。そのことも重なって、キリスト教=宗教をひとつテーマに物語を書いてみようと思いました。
そこでいろいろと考えていったんですけど、僕は聖書の中でもヨブ記に心を惹かれるところがあって。ご存知の方も多いと思いますけど、ヨブ記はほんとうに悲惨な話なんです。簡単にまとめると神がサタンに善良なヨブにひどい試練を与えることを許したことから、ヨブはとんでもない目に遭う。サタンもひどいけど、神様もちょっとひどいと思うところがあって。なんとも不条理なんですけど、ゆえに考えさせられるところもあって、僕はなぜか心惹かれるところがある。それで、このヨブ記をモチーフにひとつ物語を書こうと思いました。
――その物語は、臨床心理士の詩織が、娘を自死で失ってしまうところから始まります。その後、詩織はクリニックを退職して図書館で無料相談室を始める。しかし平静を装ってはいるけれど、娘の死をいまだ受け入れられず、その死からも立ち直っていない。
詩織の置かれた状況をみて、「親としての責任」というテーマが過去の短編3作にもあった気がしました。親であることが足枷になって、親であることに必要以上にしばられてしまう。詩織もそういう人物です。
そう言われると確かにですね。いま言われるまで自分ではまったく意識していませんでした。なんでだろう。
自分の家族に関して言うと、そういうしばりは一切なかった。どこか親であっても他人というか。親だからといって自分の子どものことのすべてがわかるわけではない。子どもだからといって自分の親のすべてがわかるわけではない。親が言ったことに子どもが必ず従う必要はないし、子どもが言ったことに親が必ずしも答える必要はない。僕の家族はそんなスタンスで、親も子も自由で自主性に任せるスタンスでした。それが当たり前でした。だから、社会に出てちょっと衝撃を受けたというか。友人や知人と話すと、親の言うことは絶対とか、親の存在が自分にとって第一とか、ふつうに出てくる。
そのとき、あれ?もしかして自分の家族はレアケースなのかもと気づいたんですよね。周りを見てみると、親は「子どものために」、子どもは「親のために」といった感じで、「親としてこうあるべき」「子どもとしてこうあるべき」といったことにしばられて悩んでいる人がけっこういる。
自分は自由きままでそんなことがなかったから、逆にそういった状況にいる人に興味があって。それが自然な形で作品に出て、そういう人を描いてみたいとなっているのかもしれません。
――もうひとつ過去の短編と共通点をあげると、ふいに何かが訪れる、ふいに予期せぬことが起こる。そのことも共通している気がしました。
これは明確に自分の中にあります。いや、日常を生きていて、ほんとうに怖いことや悲しいことというのは予期せぬところで起きるなと思うんです。ふいにやってくることが実感としてある。平凡だった日常を突然壊すことってあるんです。
だから、他人からみると「こんなこと突然すぎるでしょ。作り物でしょ」ということを、僕の中では「いや、ありえる。現実的でリアリティがある」というものとしてとらえているところがある。こういう考えが根本にあるので、そういう設定になるのだと思います。

©elePHANTMoon
――話を作品の内容に戻しますが、カウンセラーをする詩織は、教会の神父の長谷川から、ある問題を抱えている信徒の辻村の話をきいてあげてほしいと頼まれる。ところが辻村は詩織を拒否。さらに神父の長谷川も辻村からの信頼を失ってしまう。このことで詩織も長谷川も自身の無力を味わい、心身共に疲れ果て、長谷川は体に異変をきたす。
ある意味、不条理な目に遭う詩織と長谷川からは、真の救済とはなにか、人は人の心を救うことができるのか?といった答えのなかなか出ない問いが浮かび上がります。
一方で、物語としては後半になるほどホラー色が強くなり、詳細は伏せますが怒涛の展開が、しかもまったく予定調和ではない展開が待っています。
はじめにお話ししたようにヨブ記がベースにあるので、無理に不条理なことにしようとは思いませんでしたけど、不条理なことに直面してしまう人間を描きたい気持ちはありました。
あと、予定調和ではないという点で言うと、最後にかかわることなので説明はさけたいんですけど、映画の後半ははじめまったく別の形だったんです。ただ、信頼のおける知り合いに脚本を読んでもらったら、その部分を「うまいね」と言われた。これがショックでした。変だねとか面白いね、じゃなくて、「うまいね」と言われたのは初めてで、たぶん収まるところに収まっているということで。つまり想定の範囲内にうまく収まっているということ。で、自分も初長編ということもあり伝わりやすくというのがあって、おそらくそうであることに気づいていた。なので、ショックを受けたし、バレたと思いました。予定調和になっちゃっているかと思って。
このことを受けて、書き直したんです。それでいまの形になったんですけど、知り合いに読んでもらったら、「マキタらしいね」と言ってくれました。
――そのシーンを含め、ホラーの描写はトライしてみていかがでしたか?有言実行で、はっきりと出てきます。
スタッフに言われました。「はっきりと出しちゃっていいんですか。はっきりと映らない方がいいのでは」と。でも、そこは「僕は出したいんだ」ということで、はっきりと登場する形にしました。
――スプラッターのシーンもあります。
やはり血が飛び出る演出はやりたくて、手間暇がかかりますけど、いや楽しかったです。あのシーンはキャストも興味深々だったみたいで、その日の出番が終わった役者もそのまま残ってみんなで見ていました(笑)。
――そういうホラーならではの衝撃的なシーンがいくつかあります。その中で思うのは、よく教会が撮影を了承してくれたなと(笑)。マキタ監督が「ここで撮りたい」と思った大磯教会ですよね?
僕も撮影の許可が下りたときはびっくりしました。まさかOKになると思ってなかったので「ほんとうですか」と聞き直しました(笑)。
さきほどお話ししたように、大磯教会を見て「ここで撮りたい」と思って今回の映画は始まったところがあったので、当たって砕けろじゃないですけど、まずダメもとで大磯教会にお願いしてみたんです。ちゃんと台本を渡して、なにか間違いがあってはいけないので「血が出るシーンがあります」とか「神父がこんなことになります」とか、すべてをつまびらかにして説明しました。そうしたら「いいですよ」ということで、ご了承をいただきました。
撮影を許可していただけただけでもありがたかったのに、さらに信徒さんが協力的で。たとえばミサのシーンなどを指導してくださったんです。ですから、あのミサのシーンは、実際のミサと同じ正確な儀式になっています。
――キャストの方の話もききたいのですが、まず詩織役の伊勢佳世さんはどういった経緯で?
演劇をメインに活躍されているんですけど、彼女の出演している舞台をみていて、以前からいい役者さんだなと思っていました。一度だけ僕の手掛ける舞台にオファーをしたんですけど、残念ながらそのスケジュールにすでにほかの公演が入ってしまっていて彼女にお願いできなかったことがありました。
そのことが僕の中でずっと引っ掛かっていて、いつかどこかでという気持ちがありました。それで今回の映画でカウンセラー役ができたとき、伊勢さんの顔が真っ先に浮かんだんです。ご本人には失礼だと思うんですけど、伊勢さんの顔は影を感じさせるというか。詩織は自分は常識のある人間で優秀なカウンセラーであると自負しているところがある。でも、娘を自殺で失うという最悪の事態に際して、自分自身に揺らぎが生じる。そのことが彼女に暗い影を落としているのですが、その影を、伊勢さんなら出せるのではないかと考えました。
僕はわりと俳優の方は、顔で選ぶことが多い。やはり映画は映るものなので、見て説得力があるというのは大きな武器になる。思い込みが強すぎる表情や、思い悩んでいる顔など、ちょっと暗い表情を、伊勢さんの顔は滲み出してくれるのではないかと思って。伊勢さんにお願いしました。
――神父の長谷川は古屋隆太さんが演じられています。
僕は青年団の演出部に所属しているんですけど、古屋さんは俳優部所属で。伊勢さんと同様に一度どこかで自分の作品で組んでみたいと思っていました。この神父の長谷川に関しては、あまり悟っていないといいますか。神父ではあるんですけど、いい意味で、神父っぽくない。神に仕える身ではあるんですけど、あまり宗教色がなくて、僕らのそばにいてもおかしくないような人物になればと考えていました。
なので、古屋さんには、「あまり神父と考えずに演じてください」と言ったんですけど、僕の意図したことをうまくくみとって演じてくれたと思います。

©elePHANTMoon
――ここからはこれまでのキャリアについて伺いたいと思います。マキタ監督は演劇から脚本、テレビの演出などほんとうに幅広く活躍されていますけど、この世界に進むきっかけは、映画だったのですか?
そうですね。母親がホラーやオカルトが大好きな人で。初めてみた映画が今でも覚えてえいますけど、母に連れられていった『悪魔のいけにえ』と『死霊のはらわた2』の2本立てでした。
それを小学生のときに映画館でみて、どっぷりはまりました。僕の中で映画=オカルト&ホラーで、しばらくそれしかみていなかったです。それから父親も映画が大好きで。父の方はマフィア、ギャング映画ファンでした。
たぶん夕飯を食べ終わったら、家族でバラエティ番組とかホームドラマを見るというのが一般家庭の定番のような形かなと思うんですけど、うちはホラーとかギャング映画とか、血生臭い映画がテレビから流れていました(苦笑)。
これが原体験で、高校で進路を決めるとなったとき、やはり好きな映画をやってみたいと思って、日本映画学校に入学しました。そこで映画を学んで卒業して、助監督の仕事を始めて、そこから映像の制作会社に就職してディレクターをしていました。ディレクターをしていたら、偶然、友人から頼まれて演劇の脚本を書いてみた。その流れでそのときの友人の誘いで気づけば演劇も始めていました。それから、会社を辞めて、実はパン屋もやっていたんですよ。かなり好評で僕のパンを求めて行列ができるぐらいの繁盛店になって、辞めるときに惜しまれました(笑)。
で、そのパン屋をやっているときに、『アイノユクエ』のお話をいただいて。初めて短編を撮って、これが<SKIPシティ国際Dシネマ映画祭2013>で入選することができました。ほんとうにこの入選はうれしくて、自分にとっては大きな自信になったんですよね。
『アイノユクエ』は、ずっと映画を撮りたいと思っていたんですけど、なかなか機会がなくて……。少し映画をあきらめかけていたときに、知り合いから「撮りませんか」と話がきて撮った作品でした。だから、僕としてはようやく作ることができた映画で、それがSKIPシティという素晴らしい映画祭に呼ばれて、当時、いろいろな感想をいただくことができた。この体験があって、「もうちょっと(映画作りを)続けてみようかな」と思えたんですよね。おそらく『アイノユクエ』の入選がなかったら、パン屋を続けていたと思います。
――その後も2015年の『これからのこと』、2019年の『産むということ』と短編が本映画祭に入選。短編での3回の入選を経て、今回の長編での入選になりました。報せは受けたときの感想は?
また呼んでくださって、ありがたい気持ちでいっぱいなんですけど、正直びっくりしました。みていただければわかるようにホラーですし、血も出てエグイ場面も多々あるので、正直どうかなと思っていたんです。だから、報せを受けたときは、「ほんとうにいいんですか?」という驚きがまず先になって、そこからひと呼吸おいて喜びがわいてきました。いまでも映画作りを続けてこられたのは、SKIPシティの存在があったからなのでうれしかったです。
いまはみなさんに早く見てもらいたい。どんな感想をいただけるのか楽しみです。
『ヒエロファニー』作品詳細
取材・写真・文:水上賢治