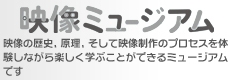【デイリーニュース】Vol.10 『助産師たち』レア・フェネール監督 Q&A
助産師の現実を圧倒的リアルさで描く
 『助産師たち』レア・フェネール監督
『助産師たち』レア・フェネール監督
国際コンペティション部門出品作の『助産師たち』は、フランスの産婦人科で働く新人助産師に焦点を当てた群像劇。慢性的な人材不足で過酷を極める労働環境のなか、真摯に命と向き合おうと理想と現実の間で葛藤する助産師の日常を、実際の出産シーンを挿入するなどリアリティとフィクションを巧みに織り交ぜて描いた。本映画祭での上映がジャパン・プレミアとなる。
ルイーズとソフィアの二人は5年間の修学を経て、「世界で最も美しい仕事」といわれる助産師として働き始める。しかし、慢性的な人材不足によるオーバーワークが常態化しているうえ、母子の命を預かるストレスにより、現場スタッフは綱渡りのような日々を過ごしていた。現実に打ちひしがれる新人助産師の二人だったが、それでも誕生という喜びを噛み締め、時に死に向き合い、成長を続けていく。
上映後のQ&Aでは、監督・共同脚本を務めたレア・フェネールが登壇。フェネール監督は、初監督作『愛について、ある土曜日の面会室』が2012年に日本で劇場公開されており、本作が長編3作目となる。
Q&Aでは、本作の助産師のリアルな現場感に圧倒された来場者から、演出方法や撮影方法に関する質問が相次いだ。フェネール監督はまず、撮影に入る前の準備段階について明かした。
「制作に入る前に約40人の助産師に会ったでしょうか。そのうち10人が今回のプロジェクトに終始親密に付き合ってくださり、編集にも協力してくれました。彼らの協力により、出産に立ち会うなど多くの経験を得ることもできました。また、脚本をすぐに書きはじめるのではなく、俳優とワークショップのようなことをしました。助産師もそこに参加してもらい、俳優のパーソナリティなどを一緒に汲み取っていきました。脚本の執筆には助産師スタッフの存在が大きかったです」。
舞台となった病院のリアルさも本作の特徴のひとつ。しかし、稼働中の病院での撮影は難しいため、一体どのように実現したのかという質問が来場者から寄せられた。
「編集の賜物ですね。舞台は本物とセットを使い分けました。工事中で実際には診療を行っていない病院にセットを組んだシーンもあります。一方で、本当に病院で仕事をしている風景を撮影したシーンもあります。合計して6つの病院で撮影しました。それらを編集でうまくまとめあげるにはエネルギーが必要ですが、編集者のおかげで勢いのある映像になったと思います」。
本作を見て驚くのが、実際の出産シーンが多く使われている点。撮影許諾や撮影方法など、一体どのように進めたのだろうか。
「出産シーンを撮らせていただけないかと尋ねると、4組に1組くらいの産婦さんとご家族の方が許可してくれました。どうして受け入れてくれたのかを考えたのですが、助産師への深いリスペクトがあったからなのだと思います。許可をもらった家族に満足してもらえるかどうかは倫理的な意味でも挑戦でした。一番緊張したのが許可してくださった皆さんの前での上映会でした」。
産婦との信頼関係の構築にはかなりの時間をかけ、できる限り誠実に接したという。「出産シーンの撮影で最も大切なことは、正しい位置にいること、絶対に出産を妨げないことです。ちょっとでも私の存在が邪魔だと感じたら、すぐに出ていきますから、とお伝えしていました。セキュリティの部分でも、性的な部分でも、気詰まりなことをしないことが重要でした。わたしにとっても初めてのドキュメンタリー。ここでの経験が、わたし自身を変えてくれたと思います。なぜなら常に自分がいる位置を意識しなくてはいけないから。それはとてもドキドキすることですし、責任のあることだと感じました」。
フェネール監督は、このようにドキュメンタリーの側面も併せ持つ本作に対して、「この作品はドキュメンタリーのリアリティとフィクションのちょうど境界線にあります。俳優がデモに参加した映像を用いたり、助産師がカメラの前で演技をしたりするなど、織物のようにリアリティとフィクションを組み合わせてできあがったのがこの作品なのです」と本作の持つ力強さを強調した。
『助産師たち』の次回上映は、7月19日(水)14時20分から多目的ホールで行われ、レア・フェネール監督によるQ&Aも予定されている。オンライン配信は7月22日(土)10時から7月26日(水)23時まで。