ニュース
【インタビュー】『夜を越える旅』萱野孝幸監督
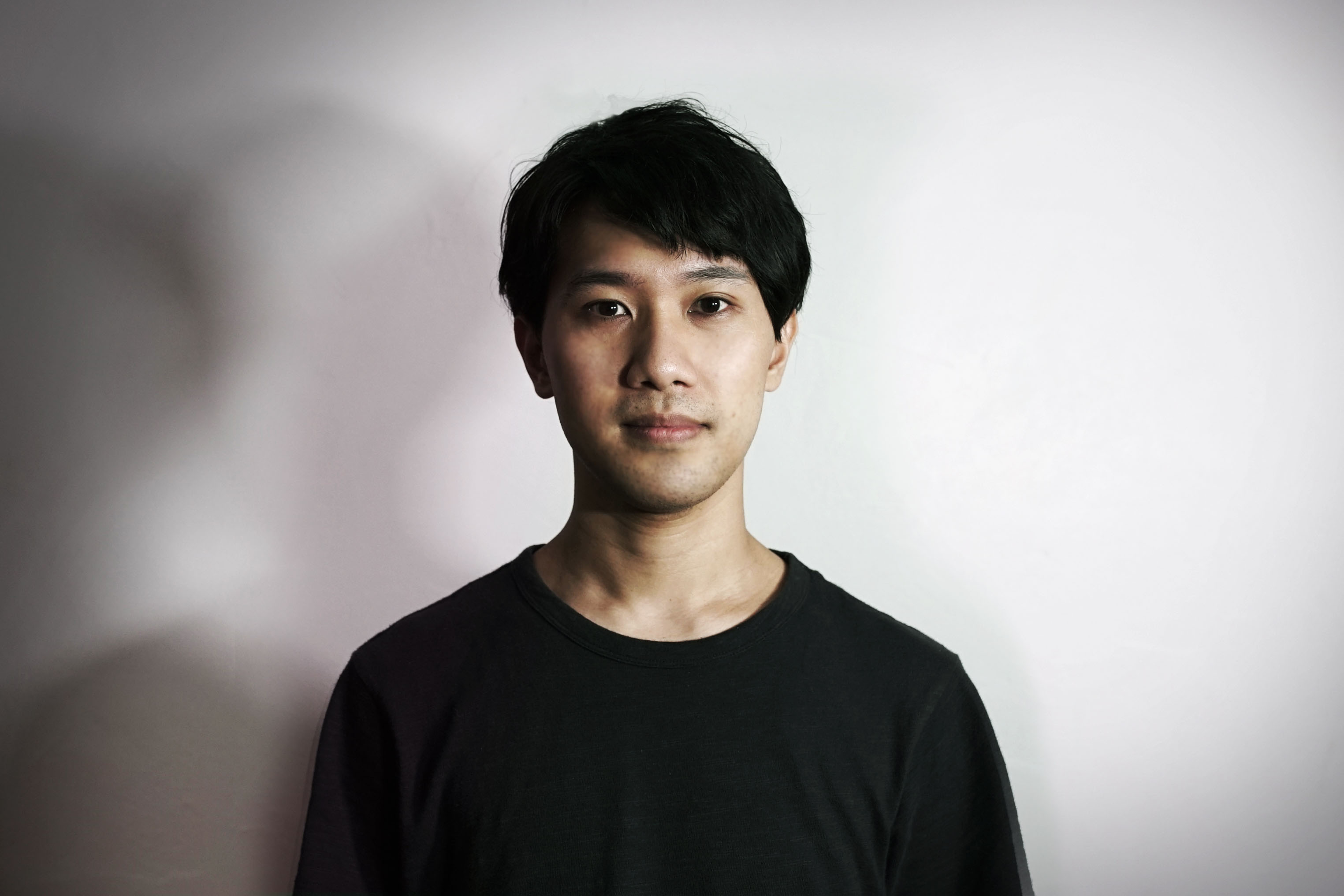
ーー今回の作品は、前半と後半でがらっと映画の表情がかわるというか。一転しますが、当初からこのようなことを考えていたのでしょうか?
そうですね。途中でシフトチェンジするような映画が作れないかと考えていたことは確かです。ストーリーもさることながら、映画自体のテイストまでもがらりと変わるような映画、一瞬にして世界が変わって観客が否応なく振り回されるような映画ができないかを考えていました。
インディーズ映画ですから、変に定石にとらわれない、予定調和で終わらない思い切ったことをしたい。予告編を見たらなんとなくオチが予想されるようなものではなく、いい意味で、観てくださる方を大きく裏切るような映画が作れないかと。
それで、何と何を組み合わせたら、そういうストーリーになるのかを考えて脚本作りに臨みました。たとえばシリアスでいきながら、途中から一転してコメディとか、いろいろと模索していたんですけど、なかなか「コレ!」と思うようなことが思いつきませんでした。
ちょうどその頃、人生最大に「ガツン!」ときたホラー映画に出会って、以来、その手の作品を浴びるように観ていて。あくまで個人的な見解ですけど、ほとんどの作品がはじめからギアがはいって一気にトップスピードに乗る。でも、それが2時間持続する作品はほんとうに一握りしかない。ホラー映画って画の作りこみとか物語の緊張感とか含めて2時間をもたせるのってそうとう高度なことが必要になってくるんだろうなと思って。
ただ、逆転の発想じゃないですけど、2時間の半分、1時間に凝縮してしまうとすごい密度の高いものになるんじゃないかなとふと思ったんです。それで、ミステリーやスリラーといったジャンルのテイストとなにかを組み合わせようという発想が生まれて。まったく別のジャンルの内容を合わせたらおもしろいものができるんじゃないかと閃いて、そうしたら、今回の作品のようなロードムービーから一転して、という流れのプロットが出来上がりました。
ーー作品は、漫画家志望の春利が、学生時代の友人たちと1泊2日の旅へ。ところがその当日の夜、応募していた漫画賞の落選の通知が。自暴自棄になりかけたところに、かつて思いを寄せていた小夜(さや)がサプライズで登場して、ここから思いもしない展開になっていきます。1本通して、ひとつのジャンルの映画にするのではなく、2つのジャンルの映画で1本の映画にするような感覚が新鮮です。その中で、主人公の春利が書いている漫画が不条理ファンタージとなっていることがその後をなにか予見させます。
主人公の春利は、はじめ小説家の設定にしようかと考えていました。ただ、考えているうちに作家における文章よりも、漫画家における絵のほうがビジュアルとしてその人物の実力というか力が明確に出るなと思って、それで漫画家の設定にしました。
それから、これはクリエイター全般に言えることですけど、物語の作り手というのは、どこか想像にとらわれる危険性を抱えている。時に想像が膨らみすぎて、頭が支配されて夢か現実かわからなくなる。そういうたがが外れた想像力の危険性というのもテーマにひとつ置きたかった。作家よりも漫画家の方が想像の飛躍が大きい気がして。それで漫画家ということにしました。
あと、ラストに関わることなのであまり詳しく触れられないのですが、春利はあることを書き残すことになる。これも作家の文章より、漫画家で描くことで残すほうが目で見て入ってくるのでいいなと思いました。それは春利が漫画家として足りないものを示すことでもあるので、そのことがストレートに伝わってくれるのではないかとも思いました。
ーー春利は、大学を卒業してそれなりの時間が経つが、いまだに何者にもなれていない。そのことを彼女に責められて、自身も強がっているものの自分に才能があるのか疑い始めている。一方で、旅を一緒にする友人らはそれぞれに自分の人生を歩んでいる。このどうにもなっていない感じが非常に前半効いていて、後半の春利の不安や焦燥につながっていくと思います。このあたりで考えたことは?
僕も含めだと思うんですけど、フリーランスの映画作家や俳優が集まると、だいたいそういう話になる(笑)。ようは成功の補償はまったくなくて、仕事が不安定で将来が見通せないといった話に。僕はどちらかというと楽観的なところがあるんですけど、生活とか将来に対する不安を払拭するために別に仕事をもって働いている人もいれば、現実逃避するように芝居に打ち込む人もいる。その多くは、漠然と不安を感じながらも、どう動けばいいかわからなくなっているところがあるような気がする。そういった、ふだん僕が肌感覚でわりと身近に感じていることが自然と投影されたのかなと思います。
あと、コロナ禍で多くの人が否応なく、自分と向き合う時間が増えたと思うんです。そのときに、悪いことばかりを想像してしまって身動きがとれなくなってしまった人がけっこういるんじゃないかなと。その見えない閉そく感や周囲の状況、周りの人間がどうしているか分からない怖さも少なからず物語や俳優の芝居に反映されている気がします。
ーーそして、なんといっても欠かせないのは、小夜の存在です。彼女の登場ですべてが一変します。
この手の作品のヒロインのイメージを一新するような存在にしたかったです。いままでにないクイーンにしたいなと。彼女に求めたのは実在感と、ある種の理想像といいますか。春利にとって都合のいい女性、彼が望む慰めの言葉や励ましの言葉を理想的なタイミングでいってくれる。そういう存在でいることで、あまりに完璧すぎて疑いがでてくるというか。
得体のしれない妖しさと違和感が生じると思ったんです。そういう人物になったかなと思います。ショートカットでパーカーを着させたのも、ちょっとポイントです。活き活きしていて闊達な感じがする一方で、どうなの?というところはありますよね。
ーー春利と小夜をつなぐアイテムとして宮沢賢治の著書「春と修羅」が出てきます。これもなにやら先を予見させます。
「銀河鉄道の夜」が大好きで。小学生で読んだとき、なんともいえない喪失感が伝わってきた。人間のいろいろな感情を知って、この体験が僕の物語作りの原体験のようになっている。ある意味、この映画の作品世界にも通じるので、「銀河鉄道の夜」にしようかと考えたのですが、ストレートすぎる気がして、春利と語感が似ているのと内容もそう遠くないということで「春と修羅」に収まりました。
ーーキャストについてもお聞きしたいのですが、主演の高橋佳成さんは萱野さんの作品にずっと出演している役者さんとお伺いしました。
そうですね。大学在学中に習作で撮ったウェブ・ドラマからの付き合いです。ほんとうに、自分の映画のキャリアは彼とともにあるといっていいです。すべての作品に出演していただいているので。役者と俳優と立場が違うので、切磋琢磨した感じはないんですけど、一緒に映画の道を歩んできた感じはあります。
僕自身、彼の芝居をみることで、監督として気づかされることが多々ありました。どの役をやるにも、結果的にその役になりきってくれて、その役に実在感をもたらしてくれる。信頼しているし、頼りにしている役者です。
ーー小夜役の中村祐美子さんは、今回が初めてですか?この役はなかなか人選に悩まれたのではないかと勝手ながら推察するのですが。
中村さんとは初めてになります。実はその通りで、小夜役はほんとうに最後までみつからなくて難航したんです。僕が求めていたのは実在感と生命力のバランスというか。両方がありすぎても困るし、なさ過ぎても困る。生命力をほのかに感じさせながらも、無機質にみえるような、そんな実在感と透明感があるような人を探していたんです。でも、なかなかみつからない。
それで中村さんは東京を拠点にしていて、ビデオオーディションだったんですけど、見た瞬間に、ぴったりだなと。自分が求めるものが備わっていた。あと、目が大きいので、すごく見られている感じがする。春利はずっと小夜のことを見ていて忘れられないわけですけど、一方で彼女に魅入られて凌駕されているところがある。だから、この目力もぴったりだなと思いました。
ーーでは、ここからはこれまでのことを少しお伺いしたいのですが、まず映画監督を目指されたきっかけは?
実は、僕が映画を本格的に観始めたのは、大学時代からで。大学を卒業してから映画を作り始めているんです。親も全然映画をみなくて、大学まではほぼ映画に触れてこない人生でした(笑)。高校のときになんとなく入った放送部で、見よう見真似ですけど、ビデオカメラを回すことを覚えて、映像のおもしろさを知りました。
その後、福岡の九州大学芸術工学部画像設計学科に進んで、そこでグラフィックスとかデザインとか、モーショングラフィックスとか、いろいろ手を出して作り始めて、その過程で趣味的に映画をみるようになり、習作で短編を作ったりしてみました。そのあたりから映画を作りたい気持ちが芽生えました。
ただ、大学時代は映画を作ったよりも、映像を作ったといった感じで。そして、大学卒業後、ようやく実行に移して一度やってみようとなって、いきなり3時間の長編を撮りました。
ーーそれが初監督作品の『カランデイバ』ですか?
そうです。『カランデイバ』は群像劇で。わりとヒューマン・ドラマの強い、地に足の着いたというか、市井の人々の物語でした。今気づいたのですが、『カランデイバ』は、6編で構成されていて、それぞれに青春ドラマであったり、サスペンスだったり、スリラー的だったりと、いろいろなジャンルの映画を横並びにして、それらが交差していくような感覚がありました。今回の『夜を越える旅』は、その逆といいますか。縦軸にして、途中でまったく表情が変わるような作品になった気がします。そういう意味で、『カランデイバ』と『夜を越える旅』に関連はないことはないかもしれません。
話を戻しますけど、『カランデイバ』は、友人やキャストに手伝ってもらって、基本スタッフは僕ひとり。出演していただいた役者さんとか手の空いている人にマイク持ってもらったりして、完全な自主映画スタイルで作った作品です。今考えると、無謀なことやったなと思うんですけど、それが僕の映画作りの原体験になって、映画作りのおもしろさに目覚めてしまった。そこから、気づけばいまも続けている感じです。
ーー以来、ずっと福岡を活動の拠点にされています。
はい。でも、別に福岡にこだわっているわけではなくて、呼ばれればどこへでも行くつもりです。ただ、福岡だからといって不便を感じることはないんですよ。いままでやってきた福岡のクルーと俳優たちでおもしろいものが作れる自信はあるので、今後も福岡を中心に九州で映画を作って、作品を全国に届けたい気持ちはあります。
ただ、福岡で閉じてしまうのは、それはそれでおもしろくないので、東京をはじめほかのエリアの俳優さんとかスタッフと交流しながら、最終的には場所とか関係なく作りたい気持ちがあります。福岡でおもしろいことやっていい映画撮っている監督や俳優がいるから、自分も関わってみたいといってほかのエリアからスタッフや役者さんがきてくれたら、うれしいですし、そういうクオリティの作品を作っていきたいです。
ーー『夜を越える旅』の撮影は昨年の10月のとのこと。コロナ禍での撮影は大変でしたか?
大変でしたね。たまたまこの脚本が自然の中が舞台で、登場人物も少ない設定で大勢のエキストラとか必要ではなかったので成立したと思います。
もっと大所帯のものだったら、無理。これならば実現可能となったところは少なからずあります。それでも、俳優はマスクを外すので、検温から検査からきちんとして万全を期して臨みました。車の送迎も人数を少なくしたりして。制作部や助監督は大変だったと思います。予防に労力を割いての撮影で。ここまで神経を使っての撮影は初めてでしたね。
ーーコロナ禍で創作のモチベーションが下がったりといったことはなかったですか?
もともと引きこもり気味でインドア派の人間なので、あまり僕自身の生活は変わらなかったんですよね。もちろん仕事が飛んだりといったことはあったんですけど、ずっと家にいて気が滅入るとかはなかったんですよ。家にずっといることがあまり苦ではないので(苦笑)。だから、周りの人が気落ちしたり、ストレスを感じたりとかメンタルをやられていることに「大変だな」と想いを馳せて心配していましたね。公演が飛んで落ち込んでいる知り合いの俳優とかいましたから。
ーーその中で、ひとつ作品を完成できたのは大きかったのでは?
そうですね。全員無事に健康を保って撮れたことはよかったです。スタッフ、キャストに感謝ですね。
ーーそういった中での入選の報せはどう受けとめましたか?
もう心底うれしかったです。毎回そうなんですけど、自分としてはおもしろい、けど、みなさんはどうだろうと不安が頭をよぎるんです。でも、選ばれたということは少なからず選考で「おもしろい」と思ってくださった方がいたわけで、すごく自信になりました。
ーー映画祭はどういう機会にしたいですか?
そんなに呼ばれたことないので正直なことを言うと、わからないです。横も縦のつながりもない僕にとっては勉強の場で、交流ができるありがたいチャンスだと思っています。それから、ふつうの劇場映画でさえ、公開の場が減っているのが現状。その中で、こういう見てもらえるチャンスができたことはうれしい。なにより福岡の俳優が多くの方の目に触れることはうれしいので、こういう俳優がいるんだと知ってもらえたらと期待しています。
あと、もちろん自分の作品の上映も楽しみなんですけど、僕自身、他の作品を観たいです。すごく気になります。作り手の本音を聞けるQ&Aもあるそうなので、どういう気持ちで作られているのか訊きたい。
僕自身、映画祭を存分に楽しみたいと思っています。
文・写真=水上賢治




