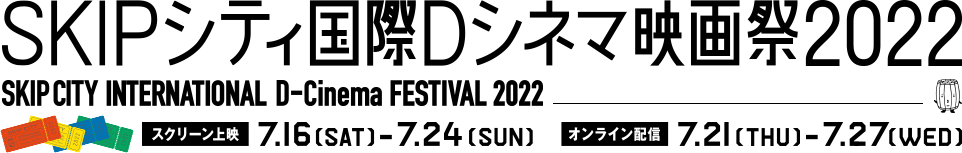ニュース
【インタビュー】国際コンペティション『とおいらいめい』大橋隆行監督
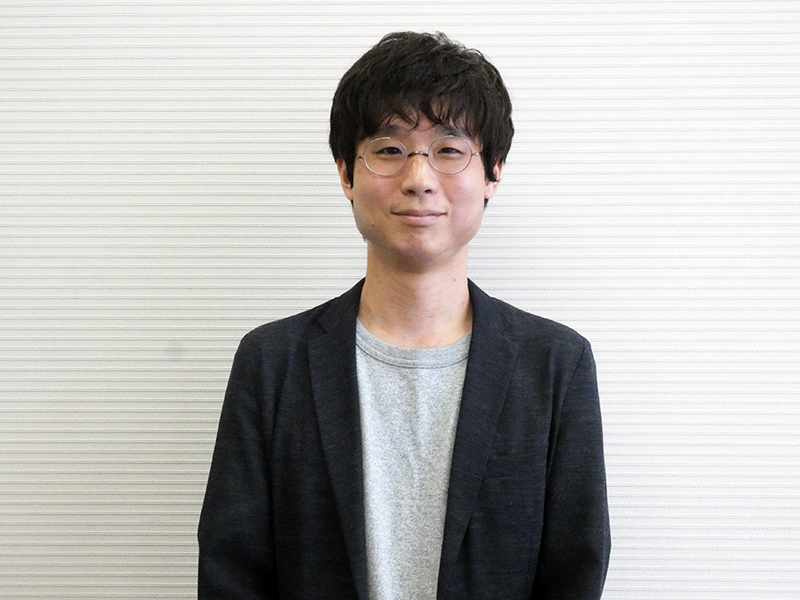
――今回の『とおいらいめい』は、本作に出演されている藤田健彦さんとしゅはまはるみさん、撮影を担当した長谷川朋史さんが立ち上げた自主映画制作ユニット「ルネシネマ」の作品になります。ルネシネマの作品は、長谷川さんが監督を務めた『あらののはて』が2020年に本映画祭国内コンペティション長編部門に選出されています。はじめに、大橋監督がルネシネマに参加することになった経緯を少しお聞きしたいのですが?
僕は、ブライダルの撮影の仕事をしているのですが、長谷川さんとはそこで知り合いました。
2018年に池袋のシネマ・ロサで僕の監督作『さくらになる』をはじめとした作品を公開したんですけど、そのときに長谷川さんが観にきてくれて、どうやら作品を気に入ってもらえたみたいで(笑)、ルネシネマの映画作りに誘っていただいたというのが簡単な経緯です。
――これは『あらののはて』の取材時に長谷川さんに伺ったことですが、ルネシネマを設立した理由のひとつとして、かつて数多くの舞台の作・演出をしていた長谷川さんがその戯曲の映画化を目指すことがあったと。今回の『とおいらいめい』は、長谷川さんの戯曲の映画化になりますね?
舞台は基本的にライブで終わってしまい、その場でみた人にしか残らない。なので、自分の手掛けた戯曲を、映画としてきちんと映像として残したい気持ちがあって『ルネシネマ』を立ち上げたといった主旨のことを僕も聞きました。
今回の場合は、長谷川さんがいくつかの戯曲をピックアップして僕に渡してくれて、『気に入ったのがあったら何か映画化してくれないか』といった感じで始まっています。
その直後ぐらいに、試しに一度組んでみようということで、長谷川さんと田口敬太さんと僕がそれぞれ監督を務めた3編からなるオムニバス映画『かぞくあわせ』を作って、その制作が落ち着いて、いよいよという感じで『とおいらいめい』にとりかかったという流れがあります。
――長谷川さんの方からいくつか戯曲の提示があったとのことですが、その中で『とおいらいめい』を選んだ理由は?
ひと言でいうと、『好み』だったんです。
長谷川さんの描く作品世界の中にある日常とSFのバランスに、僕はすごくシンパシーを感じるところがあるんです。
原作の中に「誰かひとり死ぬと、世界がひとつ終わる」というセリフがあるんですけど、この考えは、僕の中の死生観ともつながるところがあって、体感として理解できるところがある。
このセリフを作品のひとつの軸にすれば、自分なりかつ原作の色もちゃんと残した作品にできるのではないかと思いました。
――原作者の長谷川さんからなにかリクエストのようなものはあったのでしょうか?
いや、それがなくて(笑)。
2004年の戯曲ということで20年近く経っていたからか、長谷川さん自身も原作との距離ができていたみたいで、「自由にやっていいよ」と。
それどころか、わりと積極的に原作を変えるアイデアを僕にくれるんですよ(笑)。
たとえば、長谷川さんは出身地が岡山で、僕の作品世界と岡山の瀬戸内海の相性がいいのではと思ったみたいで、「岡山でのロケどう」とか、原作は双子の姉妹が主人公なんですけど、「いっそのこと三姉妹にしてみては」とか。
ほんとうに自由にやらせてくださって、結果として原作とはずいぶんと違う作品になってしまいました(笑)。
――具体的にどういう変更点があったのでしょうか?
いまお伝えしたように原作は、双子の姉妹が主人公でしたけど、三姉妹にしました。
あと、原作は一幕、一場もので、亡くなったお父さんが遺してくれたバーのようなスペースを舞台に、世界が終わる前夜の話が展開していく。ただ、主人公の姉妹は明日世界が終わることを知らない。でも、今回の映画では世界が終わることがわかっている設定になっています。
そのあたりが大きな変更点で、長谷川さんにも「全然違うなぁ」と言われました(笑)。
――まず作品は、彗星の衝突により人類の滅亡が数カ月後に迫った2020年が舞台になります。
僕はこれまでわりと、世紀末的なものSFの世界観のあるものを作ってきたんですけど、彗星が落ちて世界が終わるというような設定は避けてきたというか。
映画が好きでいろいろみてきた中で、ハリウッドのSF超大作が扱うようなストレートな設定の気がして、自主映画でそれに太刀打ちできるとは思えない。
だから、あえてトライしてこなかったんですけど、今回は原作がそうであるということでチャレンジしてもいいかなと思い切って取り入れました。
――もう世界が終わることが決まっている中、小学生のころの1999年に、ノストラダムスの予言を信じて家出したことのある長女の絢音と次女の花音、その後生まれた異母妹の音が、父の死をきっかけに生まれて初めて3人で暮らすことになる。これまで別々に暮らして微妙に距離のあった者同士の関係の変化が描かれていきます。
三姉妹の関係性を通して、どこか「家族の存在」を考えているような印象を受けたのですが?
そうですね。自分の中で、「家族」はわからないもののひとつで、今回じっくり考えてみたい気持ちがありました。
家族を考える上で大切にしたことが「音」でした。その意味合いもあって、三姉妹の名前にも「音」をすべて入れたところがあります。
なぜ、音を大切にしたかというと、誰かと一緒に暮らす、時間をともにするというのは、その人の発する音を感じながら生きることなのかと思ったんです。
ときに不快になりながらも、なんとなくその人の発する音を感じながら過ごすことができるのが「家族」なのかなと。
音は姉たちの発する音に最初はなじめない。でも、徐々に印象が変わっていく。その変化で、姉妹の関係と「家族」という存在を表現できればと考えました。
――それにしても、双子の物語を三姉妹の物語にするというのは、なかなかの大胆な改変だったと思うのですが、なぜそう踏み切れたのでしょう?
末っ子の音を演じていただいた髙石あかりさんと出会ったことが大きかったです。『かぞくあわせ』が完成して公開前に試写会を開いたのですが、当時のしゅはまさんのマネージャーを通じて、髙石さんが見に来てくれたんですね。
そのとき、まだ16歳でほんの少し会話をもった程度だったんですけど、ティーンとは思えない落ち着いた雰囲気とちょっと低音の声がすごく印象に残って。長谷川さんと「髙石さん、ちょっと気になるよね」という話になって、当時、『とおいらいめい』の話も進めていたので、「三姉妹の話にしたら、出演してもらえるかも」という話になっていったんです。
だから、髙石さんが実は、三姉妹にするきっかけになっています。
――この三姉妹のキャスティングは、完璧といっていいと思うのですが?
なんとなく、構図としては、真面目でしっかりしているのだけれど妹たちからすると頼ることのできない長女と、あっけらかんとして何も考えていないようで実は深く物事を考えている次女、一人でいると自由気ままだけど、姉二人といるとどうにも落ち着かない末っ子の三女、みたいなことを考えていました。
その中で、髙石さんはほぼ当て書きに近い形で音を書いていったところがある。一方、長女の絢音と次女の花音に関しては、オーディションで決めたんですけど、吹越ともみさんと田中美晴さんをみた瞬間に、直感で「この二人だ」とピンときたんです。
オーディションの時点では、脚本はほとんどできていなくて、架空のシーンを演じてもらいました。
ある程度の人数だったので、組分けして演じていってもらったんですけど、吹越さんと田中さんはたまたま同じ組で、二人を見た瞬間に「この二人だ」と思ったんです。
なぜ、ピンときたかというと、オーディションを開催するよりも前に2度ほどシナハンで岡山を訪れて、瀬戸内海の風景を眺めながら、なんとなく三姉妹が暮らす街並みをイメージしていました。実のところ、今回の作品は物語よりも、キャスティングよりも先に、三姉妹が暮らしている街並みが先に生まれました。
それで、吹越さんと田中さんにオーディションでお芝居をしてもらったときに、イメージした街並みに居る二人が違和感なく想像できたんです。
その直感に間違いはなかったと思っているので、そういっていただけるのはうれしいです。
――ポスタービジュアルにもなっているあの夕暮れの長回しのシーンは、当初からあのようなショットを狙っていたのでしょうか?
長回しのシーンに関しては長いことどうするか悩んでいました。
あるとき、三姉妹が特に言葉を交わすわけでもない、何気ないやりとりに過ぎないけれども、なんだか忘れがたいかけがえのない瞬間を分かち合っているような、あのシーンのイメージが頭にふっと浮かんだんです。世界の終わりを迎えようとする三姉妹を、観客のみなさんにも見届けてほしいなと。
あのシーンを撮るチャンスは1日1回で、時間的に2日で2回しかなかったんですけど、やってみるまで成功するかわかりませんでした。1日目の1回目でうまくいかなかったら、アドリブでなく、全部セリフをつけてみようとか考えていました。
ただ、1日目にやってみたら、まったく問題なかった。ほぼ三姉妹にお任せだったんですけど、僕の想像をはるかに超えるシーンになった手ごたえがありました。
映画を作っていて楽しいのは、脚本の段階では自分だけの枠に入っていたものが、いろいろな人の感性が混じり合って予想もしないものになるときがあること。
まさにこのシーンはそうで。役者さん三人のお芝居と長谷川さんの切り取る画が相まって、僕の当初考えていたことを軽々と超えて、究極のシーンへとなってくれた。
三人の役者さんは長回しでどこで終わりにしていいかわからなくて、大変だったみたいなんですけど(笑)。僕としては自分の想像を超えてくれるシーンになってくれてうれしかったです。
――そのシーンを含めて、すばらしい映像になっていると思います。撮影は原作者でもある長谷川さんが担当されています。
原作については何ひとつ口を挟まれなかったと話しましたが、唯一提示された条件がこれだったかもしれません。
撮影は「自分がやりたい」と。
これまで僕は撮影のカメラマンについては、好みがばっちり合う人としか組んでこなかったんです。自分と似た感性や映像にこだわりのある人にしか頼んでこなかった。
ただ、今回はこれまでとは少し考え方をかえて、100%合う人ではなくて、異なる感覚をもっている人と組んでみたい気持ちがあったんです。自分と異なるセンスをもった人と組むことで、なにか新しい発見や発想も生まれるんじゃないかと思って。
で、長谷川さんは、『かぞくあわせ』のときにの撮影をみていて、自分とは微妙に違うところがある。なので、「いいチャンスだな」と思って、「よろしくお願いします」と長谷川さんにお願いしました。

©ルネシネマ
――ここからはこれまでの歩みについて聞きたいのですが、映画作りを志すきっかけは?
もともとはCGを学びたくて、尚美学園大学に進んだんですけど、CGの授業に入る前にまず実写の授業があったんです。
そこでたまたま一緒に組んだ友だちと、「じゃあ夏休みに映画を作ろうよ」という話になって、僕は脚本を書き始めた。そこから映画作りにはまっていきました。
で、脚本を書いたのはいいんですけど、当然と言えば当然ですけど、誰も撮ってくれない(苦笑)。じゃあ、自分で撮るしかないとなった。
だから、監督を始める気はまったくなくて、仕方なくはじめて今に至っている感じです(笑)。
――当初は、どちらかというと映像制作の方に進みたかった?
そうですね。高校生のときに進路でどうしようとなったとき、山崎貴監督の作品、白組の仕事をみて、なにかCGなどで映画作りにかかわれないかなと当初は考えていました。
ただ、先ほど話したとおり、大学でいいメンバーができて、映画を撮りはじめた。その仲間でなんとなく卒業後も映画を撮っていたこともあって、わりと映画作りを継続していく機会が続いていったんですね。前で話したように映画祭にはまったくひっかからなかったのですが(笑)。
そして、2014年に『押し入れ女の幸福』がSKIPシティで短編コンペティション部門の最優秀作品賞を受賞して、そこでまた出会いがあって映画を作る仲間が増えた。その後も、今回の長谷川さんに出会ったりして、いつかどこかで途切れるだろうなと思いつつ、ここまで監督を続けることができています。
――では、今回の国際コンペティション部門の入選について聞きたいのですが、その前に大橋監督は、2013年に製作した短編映画『押し入れ女の幸福』がSKIPシティ国際Dシネマ映画祭2014の短編部門グランプリを受賞しています。このときの経験をまず振り返っていただきたいのですが?
学生時代から映画を作り始めたのですが、作品を完成させてもどこの映画祭にもひっかからず、紋々とした日々を長いこと過ごしていて……。ほんとうに初めて選ばれて出品することができたのがSKIPシティでした。
自分の作品を大きなスクリーンでみるのも、映画祭自体に参加するのも、なにからなにまで初体験ですべてが新鮮でした。僕にとっての映画祭の原体験になっているといっていいです。
ほかの作品をみたらほんとうにレベルが高くて、「まあ自分の作品は賞を受賞することはないだろうと」と思ってわりと映画祭を満喫していたら、賞までいただいてしまって……。まったく自分の中では予期せぬ出来事だったので、受賞後もしばらくは実感がなくて、現実なのか夢なのかといった感じで心がフワフワしていたことをいまでも覚えています。
――今回の国際コンペティションでのノミネートはどう受けとめましたか?
素直にうれしかったです。ただ、国際コンペティションということで、「海外の作品と自分の作品が並んでどういう評価を受けるのか」と冷静に考えると、ちょっと気が重いというか。プレッシャーがないといったら嘘になりますね。
あと、ひとつホッとした気持ちがあります。
『押し入れ女の幸福』の受賞時に、「次は長編で戻ってきたい」という主旨のことを宣言していたので、有言実行でSKIPシティに帰ってくることができたなと思っています。
振り返ると、SKIPシティは僕にとって要所で縁のある映画祭で。『押し入れ女の幸福』も、その数年前に撮った初長編が最終選考まで残っていたとの連絡を映画祭サイドからいただいて、その悔しさをバネに作ったんですよね。
そして、先ほどのように「戻ってきたい」と宣言して、今回戻ってくることができた。そういう意味で、僕にとってSKIPシティは映画を作っていくモチベーションになってくれたところがある。
非常に自分の中で思い入れの強い場なので、こうしてまた上映の機会をいただけたことに感謝しています。
『とおいらいめい』作品詳細
取材・写真・文:水上賢治