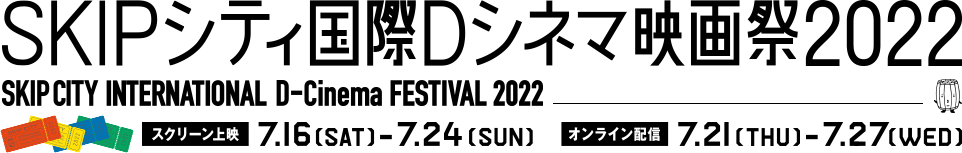ニュース
【インタビュー】国内コンペティション長編部門『ブルーカラーエスパーズ』小林大輝監督

――まず、作品の話に入る前に、今回の『ブルーカラーエスパーズ』を制作するに至った経緯を教えていただければと思うのですが?
日本大学芸術学部映画学科を卒業したのが2018年3月で、そこから某組の助監督として入って、地獄のような日々を送っていました。まあ、現在進行形で味わっているんですけど(笑)。
その中で、2019年の年末に知り合いから飲み会に誘われたんです。劇場の方も来ているのでちょっと顔を出してみないかと。
僕はあまりそういう場がすきじゃない。ただ、当時、助監督をまがりなりにも2年間頑張って続けていたんですけど……。
周りの知り合いがウェブドラマを手掛けたりしているのに、助監督の自分にはまったくそういうチャンスが巡ってこない。なので、そういうコネクション作りみたいなこともしていかなきゃダメなのかなと思って参加したんです。
それで行ってみたら、その劇場関係の方が、僕の日本大学芸術学部映画学科の卒業制作作品『アウェイ』をみてくれていた。これも何かの縁かなと思って、厚かましいんですけど、「上映してくださいよ」とお願いしたんです。
するとその劇場関係の方が、『アウェイ』は30分の作品なんですけど、新作と合わせて90分にしたら考えてもいいよと。これが制作に踏み出すきっかけでした。
――『ブルーカラーエスパーズ』は、超能力者たちを主人公にしたSF映画ですけど、はじめからSF映画を考えていたんですか?
いえ、最初は超能力ものとかまったく考えていなかったです。
自作ではありますけど『アウェイ』はお気に入りの作品だったので、僕としては最初、その続編にしようかと考えました。
ただ、いざ脚本を書き始めたとき、はたと思ったんです。「これまで一般公開もされて、ほとんど誰もみたことのない短編映画の続編をどこの誰がみたいんだ」と(苦笑)。それで新たな作品を考えようと思いました。
当時、仕事でいろいろとフラストレーションがたまっているときで、助監督をしている自分の話にしようかと考えました。
でも、そうなると劇中劇で、映画の現場を作らないといけなくなるから、単純に機材が倍ぐらい必要になる。それを借りるだけでもどんだけお金がかかるんだよと思って「無理だ」となった。
あえなくまた方向転換をしていろいろと考えていたんですけど、ふと、地元でのことを思い出したんです。
どういうことかというと、自分ではまったくそう思わないんですけど、たまに地元に帰って、愛知の田舎町なんですけど、知人にあって話していると、僕がある女優さんの作品に携わっているだけで「すごい」ということになる。「えっ、あの女優さんと仕事しているのすごい」みたいなことになる。
いや、その女優さんはすごいかもしれないですけど、僕はぜんぜんすごくないし、そんなことで自分を誇れない。なんともいえない居心地の悪さをものすごく感じるんです。
その感覚を思い出したときに、「これ、超能力者で表現できるのではないか」と思いついた。
客観的にみると、超能力者って特別な存在で。一般人からするとすべての超能力者が等しく特別な能力の持ち主にほかならない。
けど、その超能力者たちの中にも、ヒエラルキーがあって、超能力者なのに自分が特別とは思えない、誇れないやつがいたら、いまの自分をうまく重ね合わせられるのではないかと思って、そこから脚本を書き始めました。
――では、その時点では、超能力者が主人公というだけで脚本を書き始めた?
いえ、主演だけは加藤(千尚)と決めていました。
彼は大学の同期なんですけど、『アウェイ』も主演を務めてもらっていて。個人的に彼がタバコを吸う姿がすごく好きで、自分の作品でタバコを吸わせたいとずっと思っていた。
その時期、彼も僕と同じく鳴かず飛ばずでやさぐれていたので(笑)、ちょうどいいと思って、主演は加藤ということだけ決まっていました。
――自主製作でSF映画、しかも超能力を扱うというのはなかなかハードルが高いと思うのですが?
正直、僕自身も、インディーズでSF映画って鬼門かなと思いました。どうしても映像にスペクタクル感が求められるところがあるので、低予算だと安っぽくなってしまう。
ただ、自主制作や学生映画に多い、自分が世界や社会から認められないといったようなよくある私的な映画にはしたくなかった。それでは箸にも棒にも掛からないだろうと思って、なにかほかにない強みを考えたときに、自主ではあまりないSFはいいんじゃないかと。
僕はSFにも超能力にもマニアのような強い思い入れがない。こだわりがない分、SFや超能力に客観的に適度な距離をもって描くことができるのではないかと思いました。
また、SFの設定は使いますけど、そこに注視するよりも、きちんとしたドラマを成立させたいと考えました。
ストーリーをきちんとした見ごたえあるものにすればいけるんじゃないかと考えました。のちのち、「めちゃくちゃ甘い考え」と気づくんですけど(笑)。
――作品は、人の記憶を消す超能力を持つ旬作が主人公。ただ、彼はその能力のレベルが低いため、いい金になる仕事が回ってこない。そんな折、高校生、輔(たすく)に自分の仕事がバレてしまう。ところが実は輔もエスパーで仲間に引き入れて、行動を共にすることになる。その中で、いろいろなことが起きていくのですが、まずこの旬作と輔が異色のエスパーといいますか。旬作はエスパーとしての自分の能力があまり高くないことに悩み、輔にかんしてはその能力をほぼ発揮することなく、同級生のいじめの対象になっている。こんな自分に自信のないエスパーはみたことがないかもしれません。
簡単に言うと、旬作は大学に入ってからの僕を、輔は大学に入る前の僕を投影しています。
あまり詳しい説明は控えますけど、旬作は超能力者ですけど、もう半径5メートルぐらいしかみえていない視野の狭い、器の小さい人物でヒーローではない。
悪態ついて、やさぐれていて、決して褒められた人物ではない。僕自身もそういう人間ということです(苦笑)。
一方、輔は、現実の世界を知っているようで知らない。かつて僕はそういう感じだったいうことですね。
――超能力バトルのお約束のような、なにかレーザービームが出るようなCGを駆使した派手なアクションシーンはありません。ただ、巧みな演出とカット構成で視覚化できない特殊能力をきちんと感じられるものになっているところがひじょうに考えられていると思いました。
派手なバトルシーンはできない、エキストラが豊富にいるわけでもなければ、CGも使わない。
そういう中で、超能力者同士の能力レベルの違いや、ものすごい能力をもった者の脅威感といったことをどう表現すれば伝わるものになるのかひじょうに悩みました。
そもそも彼らが超能力者にみえるようにできているのか、不安でした。もうそこは創意工夫で乗り切るしかなかったので、そういってもらえるとありがたいです。
あと、役者が頑張ってくれて、役に血を通わせてくれたところも大きかったと思います。ただ、大変なので、もう一生、SF映画には手をださないかもしれません(苦笑)。
――たとえば、旬作が記憶を消すあの指の動き。ひじょうに納得させる動作になっていると思います。
あれはいかに自然にみせるかがひじょうに重要だと思って。
加藤にいつもタバコを吸うときの動作のように、それぐらい馴染ませて、相手が警戒心をもたない自然な動作にしてほしいと伝えました。1日最低200回はあの動作をしてなじませてくれとお願いしました。本人が実際に200回練習していたかはわかりませんけど(笑)。
――その旬作を演じた加藤さんですが、ひじょうに存在感のある役者さんで、強く印象に残りました。
さきほど少し触れたように加藤は大学の同期なんです。
でも、大学の4年までひと言も話したことがなかったんです。4年のときに、『アウェイ』を作ることになって、彼に合うかなと声かけて、そこから親しくなりました。
純粋にいい顔しているなと思うし、見た目でいうと、ケンカが強そうにみえてただものじゃない感じがある。ただ、強面ですけど、彼自身はすごく優しい人間で、腰もめちゃくちゃ低い。
で、『アウェイ』のときは、そのただものじゃない感じを全面に押し出してもらったんです。今回は逆で、めちゃくちゃ器の小さいかっこ悪いやつにしたらおもしろいかなと。
それは彼の役者としての新たな面を引き出すことにもなるかなと思いました。
彼がださく、情けなく、頼りないやつにみえたら、僕の演出は成功したかなと思っています。お互いまだまだですけど、一緒にこの世界で上がっていけたらと思っています。そう甘くはないことだと思いますが。

©daikikoboayashi2022
――では、ここからは監督を目指すようになったきっかけをお伺いしたいのですが?
実は、この監督に憧れてとかではなくて、きっかけは映画とはまったく関係ない話なんです。
小学校6年生のときに、バスケットボールにハマって、中学に入ったら、バスケ部に入ろうと思ったんです。ところが、行く中学校にバスケ部がないことが判明した。僕としてはもうどうしようもない。
そうしたら、父親が「じゃあ、バスケ部を作るか」と言い出して、その中学に進む生徒にアンケート作って配って集計して、「これだけバスケをやりたい子がいる」という結果をもって学校にプレゼンにいったんです。「バスケ部を作れないか」と。で、なんと僕が入学するときにバスケ部ができた。そのときに、わからないですけど「自分が動けばないものって作ることができるんだ」と思ったんです。
それで、バスケ部に入ったんですけど、2年生ぐらいでもう上を目指すのは無理だとなり……。じゃあ、どうするとなったとき、昔から好きだった映画を作りたい気持ちがふつふつとわいてきた。で、親父の一件で「ないものを作ることはさほど難しくない」と思い込んでいるんで、なせばなるといった感じで高校に入ったときはもう将来は映画監督になると心に決めていました。
親父のバスケットボール部事件が、自分が映画監督を目指すことを後押ししてくれたことは確実です。あの姿を見せてくれた親父には感謝です。
――その後、映画を学ぶために日本大学芸術学部映画学科の方へ進んだ。
そうですね。映画監督になる気満々で入ったわけですけど、まあ自分より映画に詳しい人間がごまんといるわけです。愛知県の片田舎で天狗になっていた鼻をポキポキおられました(苦笑)。振り返ると、いい経験だったと思いますけど。
ただ、この大学四年間での鼻を折られる経験なんてかわいいもんで。卒業後、某組に助監督として入ったのですが、自分は大学の4年間でなにを学んだんだと思いました。
もう辛すぎて何度やめようと思ったか。仕事がハードできついこともあったんですけど、それ以上に自分が映画作る術をなにも持ち合わせていないことを痛感しました。
ただ、それでもやめなかったのは、演出部の人たちがかっこよかったからで。映画のクリエイティブなもので芸術だと思っていますけど、撮影現場に関してはほぼ肉体労働といっていい。その中で、演出部は中心になって、監督のやりたいことを汲み取って、現場をガンガン回していく。その仕事ぶりは輝いてみえた。
こういう風に、いろいろな世代のいろいろな性格の人間をたばねて、きちんと現場をコントロールしてうまく回していけるように自分もなれたら、きっと監督になったときに役立つと思ったんです。
いつかこの積み重ねが地力になって自分の監督としての力量につながると思って、いまも助監督を続けています。
――今回、こうして『ブルーカラーエスパーズ』が入選したわけですが、その知らせが届いたときの率直な感想を。
入選の報せが入ったのが、ある作品のクランクインの前日だったんです。
クランクインの前日って僕はすごく憂鬱な気分になる。また、ハードな日々が始まるのだろうなと思って(笑)。
だから、入選の報せを受けたときは一気に憂鬱な気持ちが晴れて、ものすごくハッピーな気持ちでふとんに入ることができました。それだけでSKIPシティには感謝しています(笑)。
こんなルンルンな気分でクランクインを迎えられるのはいつ以来だろうというぐらい、ほんとうにありがたかったです。
――今回の映画祭に期待することは?
正直なことを言うと、今回初めて映画祭に参加するので、どういうものなのかまったく想像できていないんです。
だから、なにを期待すればいいのか想像できないのですが、まずは作品をいろいろな人に見てもらえたらと思います。関係者以外の方にみていただくのは今回が初めてなので、どういう反応が返ってくるのか楽しみです。
僕の目標は、30歳までに自主制作ではない形で作品を撮ること。そのためのステップになればと思っています。
『ブルーカラーエスパーズ』作品詳細
取材・写真・文:水上賢治