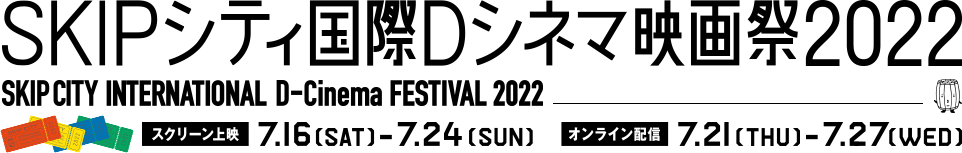ニュース
【インタビュー】国内コンペティション長編部門『ダブル・ライフ』余園園監督

――余園園監督には、来日して映画を学ぶことにした経緯からうかがいたいと思います。その前に、2015年に北京電影学院を卒業されています。ここでは何を学んでいたのでしょうか?
大学時代は、映画作りではなく、シナリオを学んでいました。
わたしは子どものころから物語を作ることが好きで、本格的に学ぶために北京電影学院に進み、シナリオについていろいろと勉強しました。
――そこからどういう経緯で日本に来ることになったのでしょう?
大学の授業の中で、是枝裕和監督の『誰も知らない』を見る機会がありました。
この作品は、わたしにとっていままでみた映画とはまったく違って、深い感銘を受けて心に深く深く残りました。そして、日本にいってみたくなりました。
すぐに働きながら独学で日本語を勉強し始めて、しばらくしたときに早稲田大学で一年間日本語を学べるプログラムがあることを知り入学を決めて来日しました。それが2018年のことです。
そのプログラムを修了後、どうするか考えていたときに、映画の専門学校のパンフレットをたまたま手にして、オープンキャンパスのようなものだったと思うですが、映像制作の現場が実際に見れるみたいなことがあって、みたらすごくおもしろそう。
ということで2019年から東京ビジュアルアーツ映画学科(現映像学科)に入学して、学校に通い始めました。
――東京ビジュアルアーツでは、『タッチ』という短編作品を発表されています。
そうですね。さきほど少し話したように、わたしは物語を作ることが大好きで、妄想をふくらませることがたくさんあります。
そういう色々と湧き出てくるアイデアをひとつにまとめてひとつの物語にしたくて、シナリオ作家を目指してきました。
まあ、体力がないのでテレビドラマや映画といった制作現場での仕事は自分では無理だろうとの思いもありました。
ただ、東京ビジュアルアーツに進んで初めて映画を撮ったときに気づいたんです。「文字で書かれた物語を映像で表現することが自分にとって一番魅力的なことだ」と。
それで映画作りについてもっと学びたい意欲がわいてきました。
――それで翌年となる2020年に立教大学大学院に進まれて、万田邦敏教授の元で演出を学ぶことになる。
そうです。
万田監督の『イヌミチ』をみてものすごく共感しました。わたし自身が描きたいことにひじょうに近いことが描かれていて、とても感銘をうけたんです。
この人のもとで学びたいと強く思いました。それで立教大学大学院に進んだのですが、実は映画美学校の方にも進みたくて。
ただ、当時、ビザの関係で映画美学校の方には進めなくて、のちに入学して実はいまも映画美学校で学んでいます。
――その中で、今回の『ダブル・ライフ』は立教大学大学院の修了制作作品になります。
修了制作作品を作らないと修了できないので、どうにかして完成させないとまずいわけですけど、何を描こうか1年間ぐらいずっと悩んでいました。
あるとき、ヴェルナー・ヘルツォーク監督の『ファミリーロマンス』を見て、家族のレンタルをする代行・代理出席サービスがあることを知ってむちゃくちゃ興味がわきました。
ちょうど、そのころ、映画美学校の方で10分の短編を作る企画があって。家族のレンタルサービスを題材にした群像劇の短編を1本作ったんです。
ただ、この作品については、万田先生からいろいろと厳しい指摘を受けました。
そして、万田先生から、「これ長編で、群像劇をやめて登場人物のひとりのこの女の子を主軸にしたら、いい物語ができるのではないか」といわれて。
この万田先生の助言から、脚本を書き始めました。
――映画美学校での実習から生まれて、立教大学での修了制作作品へとなっていったんですね。
そうなんです。
ただ、脚本を書きあげるのは至難の業で。実は女の子を主人公にしたのも、かなりあとのこと。万田先生からアドバイスをいただいていたのに、群像劇のスタイルから動けないでいた。
――そこからどうやって突破口を開いていったのでしょう?
ダンサーで振付師の砂連尾理先生との出会いが大きかったです。そのまま作品に反映されているのですが、砂連尾先生の講義を2年間受けました。
先生のワークショップや著書からいろいろとインスピレーションを得て、ストーリーができていきました。
たとえば、他人の体に触れて、そこから相手の気持ちを感じ取るといったことなど、砂連尾先生のもとで学んだことがいくつも反映されています。
それから万田先生ですね。ずっと群像劇で止まっていた私に「女性の存在にきちんと向き合って同性の物語をきちんと描いてみよう」と導いてくれました。万田先生にも感謝しています。

――作品は、ケガでダンサーの夢が断たれ、いまはダンスのワークショップの先生の助手を務めている詩織。特に大きなケンカがあるわけではないが、彼女は夫と心がすれ違っている。一緒に行くはずだったワークショップを夫にキャンセルされた彼女は、同僚から紹介された代行業の淳之介に夫役を依頼する。そこから彼女は淳之介との疑似夫婦生活にはまっていく。夫との関係、夢を断たれた現実などいろいろなものを背負った詩織の哀しみだったり、もどかしさ、苦悩といった感情の揺れが痛切に伝わってきます。
詩織は夫との関係やダンサーとしてのキャリアなど、ある意味、すでに答えがでていることを、現実問題としてなかなか受け入れられない。
それを受け容れてしまうのが怖いところもあって、つい逃げてしまう。
打ち明けると、わたし自身がそういうところがある。だから、詩織はわたしの分身なのではないかと思います。わたし自身が投影されている気がします。
ですから、なんか自分のことを語っているようで、少し恥ずかしいところがあります(笑)。
――いまの話に少しつながるのですが、詩織はどこか異邦人のようでいまの場所に居場所はなく、さまよっていて、そこには寂しさや孤独も感じられます。
そこも、やはりわたしという人間が知らず知らずのうちに反映されているのだと思います。
日本にきて4年が経ってこちらの生活にもなれましたけど、それでもふとした瞬間にいいようのない孤独や寂しさを感じる瞬間がある。そういうことも詩織には入っていると思います。
――ただ、結末に関わることなので明かせませんが、詩織はそういう苦悩を乗り越えて、力強い一歩を踏み出します。自分で自分の道を選択していきます。
現実から逃げていてはなにも始まらない。きちんと自分と向き合って、自分で決めて、新たな道を進む。
ひとりの人間として、ひとりの女性としてそうありたいなと考えました。これは詩織の決断の物語でもありますけど、わたしの決意表明でもあります。
この作品は1年半かけて完成して、ほんとうに自分としては命をかけて取り組みました。
もちろんまだまだ足りないことがある、ただひとつ言えることは、以前よりもわたし自身強い人間になれたかなと。
その強さは、詩織とつながっていると思います。
――そもそもなのですが、中国にはこのような家族をレンタルするような代行業・代理業はあるのでしょうか?
広告などみたことがあるので、たぶん都会にはあると思います。ただ、あまり聞いたことがないです。
わたし自身は、幸いなことにこれまでこのようなサービスを使ってみたいと思ったり、必要にかられたことはないです。
ただ、もしかしたら、いつの日かお世話になることがあるかもしれません。
このサービスと向き合って思ったのは、人は誰かにそばにいてほしいときがあるし、誰かと話したいときがある。人はやはり孤独ではいられない、だからこういうサービスが生まれたのかなと思いました。
――詩織を演じた菊地敦子さんの演技もその胸の内まで聞こえてくるようですばらしかったです。
ほんとうに菊地さんの演技はすばらしかったです。
撮影中はそこまで感じなかったのですが、編集をしているときに、菊地さんが詩織という人間をまるごと受け入れてくれて、何者でもない詩織になってくれたことに気づきました。
もう詩織でしかないので、自分が生み出した人物なのになんか菊地さんに奪われた気がして、ちょっと嫉妬してしまいました。
――はじめはシナリオ作家を目指していたとのことでしたが、今後は映画監督としての道を?
そうですね。物語を作って、それを映画にして表現していきたいです。
――今回、入選の連絡が来たときの感想を。
「やったー!」と思いました。夢みたいで、何度も何度もメールを見ました。
自分がこの先、映画を作っていっていいのかあんまり自信がなかったので、この入選は大きな自信をもらえた気がします。
映画祭ではひとりでも多くの方にみていただけたらという気持ちがある一方で怖さもあります。自分の分身といっていい作品なので、それがどう評価されるのか、楽しみと不安が半々です。
――恩師である万田邦敏監督には伝えましたか?
はい、「よかったね」とおっしゃってくれてうれしかったです。
『ダブル・ライフ』作品詳細
取材・写真・文:水上賢治